吉宮晴紀は、全国の古い宿を訪ね歩き、建築的な視点からその魅力をスケッチで記録しています。大学院で建築を学びながら、宿泊体験を通じて文化財の保存と活用を広める活動を続けています。
情報サイト「ときやど」や著書『ときを感じる お宿図鑑』を通じて、建物の歴史や空間の特徴をわかりやすく伝え、多くの人に新しい視点を提供しています。テレビや新聞でも紹介され、活動は全国的に注目を集めています。さらに詳しい内容を知りたくなるポイントをまとめました。
【この記事のポイント】
- 吉宮晴紀が文化財宿を巡る活動を始めた背景
- 宿泊施設をスケッチで記録する独自の方法
- 情報サイト「ときやど」と著書の役割
- メディア出演や書評掲載による社会的な広がり
吉宮晴紀って何者?経歴と建築学での活動背景
千葉大学建築学科で学ぶ大学院生としての研究

千葉大学大学院で建築学を専攻する吉宮晴紀は、歴史的建造物の保存と活用を研究テーマとしています。特に「泊まれる文化財」という切り口から、建築と宿泊体験を結びつける独自の視点を持っています。文化財は通常「鑑賞するもの」として捉えられがちですが、宿泊できる建物に焦点を当てることで、生活の場としての建築の価値を再発見する取り組みを進めています。
吉宮はこれまでに全国で400回以上宿泊を重ね、古い宿や文化財建築を実際に体験しながら研究を深めてきました。その経験をもとに、宿泊施設の間取りや断面をスケッチし、建築的な特徴を記録しています。スケッチは単なる図面ではなく、旅の記録としても機能し、建物の空間構成や歴史的背景を視覚的に伝える役割を果たしています。
また、大学院での研究活動と並行して「ときやど」という情報サイトを立ち上げ、泊まれる文化財を紹介する活動を続けています。サイトでは全国の古い宿をデータベース化し、建築的な視点から宿泊施設を整理しています。これにより、文化財を保存するだけでなく、実際に利用しながら価値を広める方法を提示しています。
さらに、著書『ときを感じる お宿図鑑』では、全国のレトロ宿をスケッチと写真で紹介し、建築の魅力を一般の読者にも伝えています。研究と出版活動を両立させる姿勢は、学術的な探究心と社会的な発信力を兼ね備えたものです。テレビ番組や新聞でも取り上げられ、学術研究の枠を超えて広く注目されています。
吉宮の研究は、文化財を「泊まれる場所」として体験することで、建築の保存と活用を両立させる新しい可能性を示しています。学問的な研究と実地の体験を結びつけることで、建築と人々の暮らしをより近いものにしています。
小田原で育ち建築に関心を深めた幼少期
吉宮晴紀は神奈川県小田原市で幼少期を過ごしました。小田原は城下町としての歴史を持ち、古い街並みや伝統的な建物が数多く残る地域です。そうした環境の中で育ったことが、建築への関心を自然に育むきっかけとなりました。
5歳から高校卒業までを小田原で過ごし、日常生活の中で古い宿や商店、歴史的建造物に触れる機会が多くありました。地域に根付いた建物は、単なる生活の場であるだけでなく、文化や歴史を感じさせる存在でもありました。幼い頃からその空間に親しんだ経験が、後の研究や活動の基盤となっています。
大学進学を機に千葉へ移り住みましたが、現在も小田原と千葉の二拠点で生活を続けています。地元に残る建物や街並みへの思いは強く、建築を学ぶ上での原点として常に意識されています。
また、幼少期から建物の間取りや構造に興味を持ち、家族旅行で宿泊した宿の空間を観察する習慣がありました。後にスケッチとして形にする活動へとつながり、建築学生としての視点を育てる土台となりました。小田原での暮らしは、建築を「生活に根差した文化」として捉える感覚を育んだ重要な時期だったといえます。
400回以上の宿泊経験から得た知見
吉宮晴紀はこれまでに400回以上の宿泊を経験し、建築学生としての研究に大きな影響を与えてきました。宿泊先は一般的なホテルに限らず、歴史的建造物を活用した宿や文化財に指定された旅館など多岐にわたります。こうした体験を重ねることで、建物の構造や空間の使い方を実地で学び、机上の知識だけでは得られない理解を深めています。
宿泊を通じて得られる知見は、単なる滞在の快適さにとどまりません。例えば、廊下の幅や階段の勾配、客室の配置など、建物の設計に込められた意図を体感することができます。さらに、浴場や食事処といった共用空間の使われ方を観察することで、建物が人々の生活にどのように寄り添ってきたかを理解する手がかりとなります。
吉宮は宿泊した施設をスケッチで記録し、間取りや断面を描き出しています。スケッチは建築的な特徴を視覚的に示すだけでなく、宿泊体験そのものを形に残す役割を果たしています。これにより、建物の空間構成や歴史的背景を多くの人に伝えることが可能になっています。
また、宿泊経験を積み重ねる中で「泊まれる文化財」という概念を確立しました。これは文化財として保存される建物を、実際に宿泊できる場として捉える視点です。宿泊することで建物の価値を体感し、保存と活用を両立させる新しい方法を提示しています。
こうした活動は著書『ときを感じる お宿図鑑』にも結実しており、全国のレトロ宿をスケッチとともに紹介しています。宿泊体験を重ねてきたからこそ描ける視点が、読者に建築の奥深さを伝えています。吉宮の400回以上の宿泊経験は、研究者としての探究心と実践的な学びを結びつける重要な基盤となっています。
宿泊施設の間取りや断面を描くスケッチ活動
吉宮晴紀は宿泊した施設の間取りや断面をスケッチし、建築的な特徴を記録する活動を続けています。スケッチは単なる図面ではなく、旅の記録としての側面も持ち合わせています。宿泊体験を通じて得た空間の印象を、建築学生ならではの視点で描き出すことで、建物の構造や歴史をより身近に感じられる作品となっています。
スケッチは平面図だけでなく断面図を意識して描かれており、柱や壁のつながり、増築部分の構造などが視覚的に理解できるよう工夫されています。宿泊施設は長い歴史の中で改修や増築を繰り返していることが多く、断面を描くことでその変化を読み解くことができます。こうした視点は、一般的なガイドブックには載らない情報を補う役割を果たしています。
制作方法はシンプルで、宿泊中に間取りを確認し、B5サイズの無地ノートにボールペンで下書きなしに描き進めるスタイルです。現場で得た印象をそのまま線に落とし込み、後に宿の主人から聞いた話や自身の観察をメモとして加え、帰宅後に完成させています。即興性と観察力が融合したスケッチは、建築の専門性と旅の臨場感を同時に伝えています。
これまでにスケッチした宿は100軒を超え、全国各地の文化財宿やレトロ建築が対象となっています。東北から九州・沖縄まで幅広く訪ね歩き、選りすぐりの事例を描き残しています。スケッチはSNSで発信され、多くの人の関心を集めたことから、後に『ときを感じる お宿図鑑』として出版されました。
この活動は、建築を学ぶ学生としての研究と、文化財を広く伝える社会的な役割を兼ね備えています。宿泊施設をスケッチで記録することで、建物の空間構成や歴史的背景を後世に残す試みとなり、文化財の保存と活用を考える上で重要な視点を提供しています。
古い宿を巡る旅と建築的視点の融合

吉宮晴紀は全国各地の古い宿を訪ね歩き、建築的な視点からその価値を記録しています。宿泊を通じて得られる体験を単なる旅の思い出に留めず、建物の構造や空間の成り立ちを丁寧に観察し、スケッチとして残しています。これにより、古い宿が持つ歴史や文化を、建築学の知識と結びつけて伝える活動を続けています。
訪れる宿は、江戸から昭和初期にかけて建てられた旅館や、銀行建築を改装したホテルなど多様です。例えば、豊岡市の「TOYOOKA1925」は大正期の銀行建築を宿泊施設として再生した事例であり、吉宮はその空間を体験しながらスケッチで記録しました。こうした事例は、文化財を保存するだけでなく、現代の生活に活かす方法を示しています。
古い宿を巡る旅は、建築の研究と密接に結びついています。宿泊することで、廊下の配置や客室の並び、増築部分の構造などを体感的に理解することができます。これらの観察は、図面や写真だけでは伝わりにくい建物の「使われ方」を知る手がかりとなっています。
また、吉宮は宿泊した宿を「泊まれる文化財」として紹介し、情報サイト「ときやど」で発信しています。文化財を鑑賞する対象としてではなく、実際に泊まることで価値を体感できる存在として位置づける視点は、多くの人に新しい発見をもたらしています。
この活動は著書『ときを感じる お宿図鑑』にも反映されており、全国のレトロ宿をスケッチとともに紹介しています。旅と研究を重ねることで、古い宿が持つ文化的・建築的な価値を広く伝え、保存と活用を両立させる新しい可能性を提示しています。
大学院休学を経て出版準備に専念した経緯
吉宮晴紀は千葉大学大学院で建築学を学びながら、文化財として残る宿泊施設を研究対象にしてきました。その活動の中で描きためたスケッチや宿泊体験をまとめ、広く伝えるために著書の出版を決意しました。出版準備に集中するため、大学院を一時休学し、執筆と編集作業に専念しました。
休学を選んだ背景には、SNSで発信していたスケッチが多くの人の関心を集め、より広い層に届けたいという思いがありました。これまでに訪ねた宿は100軒を超え、文化財としての価値を持つ建物から観光地の隙間にある宿まで幅広く記録しています。こうした膨大な資料を整理し、一冊の本にまとめるには時間と集中力が必要でした。
出版にあたっては複数の出版社から声がかかり、最終的に学芸出版社から『ときを感じる お宿図鑑』を刊行しました。全国のレトロ宿をスケッチと写真で紹介し、建築的な特徴をわかりやすく伝える内容となっています。宿泊体験を通じて得た知見を活かし、建築と旅を結びつける新しい切り口を提示しました。
この休学期間は、研究者としての学びを止めるものではなく、むしろ研究成果を社会に発信するための重要なステップでした。出版準備を通じて、文化財宿の保存と活用を広く伝えることができ、学術的な探究心と社会的な発信力を両立させる姿勢が注目されています。
「建築学生の呟き」アカウントでの情報発信
吉宮晴紀はSNS上で「建築学生の呟き」というアカウントを運営し、宿泊体験やスケッチを中心に情報を発信しています。この活動は大学在学中に始まり、建築学生ならではの視点で宿泊施設の間取りや断面を描いたスケッチを投稿することで、多くの人の関心を集めました。
活動のきっかけは、コロナ禍で外出が制限されていた時期に過去の宿泊体験を振り返り、スケッチをSNSに投稿したことでした。建物の構造や空間の成り立ちを捉えた図は、一般的な旅行写真とは異なる独自の記録方法として注目され、フォロワーから高い評価を得ました。建築的な要素を取り入れた投稿は、宿泊業界を応援したいという思いとも結びついています。
「建築学生の呟き」では、文化財として保存されている宿から観光地の隙間にある宿まで幅広く紹介されています。投稿は単なる紹介にとどまらず、建物の増築部分や空間の使われ方を断面図として描き出すことで、建築の奥行きを伝えています。こうした視点は、建築を専門的に学ぶ学生ならではのものです。
このアカウントを通じて発信された情報は、やがて「ときやど」という情報サイトの立ち上げにつながりました。SNSで得た反響を基盤に、より体系的に文化財宿を紹介する場を設けたことで、活動の幅が広がりました。さらに、著書『ときを感じる お宿図鑑』の出版へと発展し、SNSでの発信が社会的な活動へと結びついています。
「建築学生の呟き」は、建築と旅を結びつける新しい視点を提供し、フォロワーにとっては文化財宿を知るきっかけとなっています。学生の立場から始まった発信が、建築研究と社会的な発信力を兼ね備えた活動へと成長していることが特徴です。
文化財宿を支援する思いと活動の原点
吉宮晴紀の活動の根底には、文化財宿を守りながら活用していきたいという強い思いがあります。文化財として残る建物は、保存のために公開されることが多いですが、実際に宿泊できる施設は限られています。吉宮は「泊まれる文化財」という視点を持ち込み、建物を生活の場として体験することに価値を見出しました。
宿泊を通じて文化財を体感することで、建物の歴史や空間の特徴をより深く理解できます。例えば、古い旅館の廊下や客室の配置、増築部分の構造などは、実際に滞在することで初めて気づく点が多くあります。こうした体験をスケッチや文章で記録し、広く発信することで、文化財宿の存在を多くの人に伝えています。
活動の原点には、宿泊業界を応援したいという思いもあります。コロナ禍で観光や宿泊業が大きな打撃を受けた時期に、吉宮は過去の宿泊体験を振り返り、SNSでスケッチを発信しました。建築的な視点から宿を紹介することで、宿泊施設の魅力を再発見し、利用者を増やすきっかけを作ろうとしました。
さらに、情報サイト「ときやど」を立ち上げ、文化財宿を体系的に紹介する活動へと発展しました。宿泊できる文化財をデータベース化し、建築好きや旅行者に役立つ情報を提供することで、保存と活用の両立を支援しています。著書『ときを感じる お宿図鑑』もその延長線上にあり、スケッチを通じて文化財宿の価値を広く伝える試みとなっています。
吉宮の活動は、文化財を「泊まれる場所」として捉えることで、保存のためだけではなく、利用を通じて価値を広める新しい方法を提示しています。文化財宿を支援する思いは、研究者としての探究心と社会的な使命感を結びつける原点となっています。
吉宮晴紀って何者?経歴や泊まれる文化財と情報発信の広がり
情報サイト「ときやど」の立ち上げと目的

吉宮晴紀は「ときやど」という情報サイトを立ち上げ、泊まれる文化財や歴史的建造物を紹介する活動を続けています。このサイトは、宿泊できる文化財を体系的に整理し、建築好きや旅行者が利用しやすい形で情報を提供することを目的としています。
「ときやど」では、全国各地の宿泊施設を対象に、建物の歴史や構造、空間の特徴をまとめています。単なる宿泊案内ではなく、建築的な視点を加えることで、宿泊体験を通じて文化財の価値を理解できるよう工夫されています。宿泊者が建物の成り立ちや背景を知ることで、滞在そのものが文化体験となるよう意図されています。
このサイトの立ち上げは、吉宮がSNSで発信していたスケッチ活動から発展しました。多くの人が文化財宿に関心を寄せるようになり、情報を整理して提供する必要性を感じたことがきっかけです。文化財宿は数が限られているため、訪れる人にとって信頼できる情報源が求められていました。
「ときやど」は、宿泊施設の紹介だけでなく、文化財を保存しながら活用する意義を広める役割も担っています。建築学を学ぶ立場から、文化財を「泊まれる場所」として捉える視点を提示し、保存と利用を両立させる新しい方法を示しています。
この取り組みは、著書『ときを感じる お宿図鑑』にもつながり、スケッチと文章で文化財宿を紹介する活動へと発展しました。情報サイトと出版活動の両輪で、文化財宿の存在を広く伝え、建築と旅を結びつける新しい文化の形を築いています。
『お宿図鑑』出版とスケッチによる宿紹介
吉宮晴紀の著書『ときを感じる お宿図鑑』は、全国の古い宿をスケッチと写真で紹介する一冊です。建築を学ぶ立場から、宿泊施設の間取りや断面を描き出し、建物の特徴を視覚的に伝えています。単なる旅行ガイドではなく、建築的な視点を加えることで、宿泊体験を文化的な学びへと昇華させています。
本書には、東北から九州・沖縄までの宿の中から選りすぐりの35軒が掲載されています。江戸時代に建てられた北温泉旅館や、重要文化財に指定されている萬翠楼福住など、歴史的価値の高い建物が含まれています。これらの宿は、長い年月を経てもなお宿泊できる状態にあり、文化財を「泊まれる場所」として体験できる貴重な存在です。
スケッチは、外観だけでなく内部の構造や空間の成り立ちを丁寧に描いています。柱や梁の配置、増築部分のつながりなど、建築的な要素を断面図として表現することで、宿泊者が気づきにくい建物の特徴を伝えています。図面のような精密さと旅の記録が融合した作品は、建築に詳しくない読者にも理解しやすく、宿の魅力を身近に感じられるものとなっています。
出版に至るまでには、吉宮がこれまでに描きためた100軒以上のスケッチが基盤となりました。SNSで発信していた活動が注目を集め、より広い層に届けたいという思いから出版を決意しました。大学院を一時休学し、資料の整理と執筆に専念した結果、建築と旅を結びつける独自のガイドブックが完成しました。
『お宿図鑑』は、文化財宿の保存と活用を広める役割を果たしています。宿泊を通じて建物の価値を体感できるという視点は、文化財を守るだけでなく、利用することでその存在を未来へつなぐ方法を示しています。建築学の知識と旅の体験を融合させたこの本は、文化財宿を知る入り口として、多くの人に新しい発見を提供しています。
「マツコの知らない世界」でのテレビ出演
吉宮晴紀は、TBS系の人気番組「マツコの知らない世界」に出演し、「泊まれる文化財の世界」を紹介しました。放送は2024年2月13日に行われ、全国の歴史的建造物を宿泊施設として活用する事例を取り上げました。番組では、古い旅館や文化財指定の宿を実際に体験した視点から、その価値を伝えています。
番組内では、江戸時代から続く旅館や、古民家をリノベーションした宿、さらには元遊郭を活用した宿など、多様な事例が紹介されました。これらの宿は単なる宿泊施設ではなく、歴史や文化を体感できる場として位置づけられています。吉宮は建築学生としての知識を活かし、建物の構造や空間の特徴をわかりやすく解説しながら、宿泊することで文化財を身近に感じられることを伝えました。
この出演は、吉宮が立ち上げた情報サイト「ときやど」や著書『ときを感じる お宿図鑑』と連動する活動の一環でもあります。SNSでの発信から始まった取り組みがテレビ番組にまで広がり、文化財宿の存在をより多くの人に知ってもらうきっかけとなりました。番組を通じて、文化財を保存するだけでなく、実際に利用することで価値を広めるという視点が広く共有されました。
また、番組では「この春行きたい泊まれる文化財」として、世界遺産に登録されている仁和寺や、最新の古民家リノベーション宿なども紹介されました。これにより、文化財宿が観光や旅行の新しい選択肢として注目されるようになりました。吉宮の出演は、建築学の研究を社会に発信する場としても大きな意味を持ち、文化財宿の保存と活用を支援する活動の広がりを示すものとなりました。
NHK「あさイチ」「おはよう日本」などでの紹介
吉宮晴紀の活動はNHKの番組でも取り上げられ、全国的に注目を集めました。「あさイチ」や「おはよう日本」では、文化財を宿泊施設として活用する取り組みが紹介され、建築と旅を結びつけるユニークな視点が広く伝えられました。
番組では、吉宮が描いたスケッチをもとに、古い宿の構造や空間の特徴が紹介されました。宿泊体験を通じて得た知見を図として表現することで、文化財の保存と活用を両立させる新しい方法が示されています。視聴者にとっては、文化財を「泊まれる場所」として体験できるという発想が新鮮であり、建築の専門知識を持たない人にも理解しやすい形で伝えられました。
「あさイチ」では、文化財宿を訪ねる旅の様子が放送され、宿泊することで建物の歴史を体感できることが強調されました。「おはよう日本」では、著書『ときを感じる お宿図鑑』の出版も紹介され、スケッチを通じて文化財宿の価値を広める活動が注目されました。これらの番組出演は、研究者としての活動を社会に発信する大きな機会となり、文化財宿の存在を全国に知らせるきっかけとなりました。
テレビでの紹介を通じて、吉宮の活動は建築学の研究にとどまらず、観光や地域文化の振興にもつながるものとして評価されています。文化財を保存するだけでなく、実際に利用することで価値を広めるという視点は、多くの人に新しい発見をもたらしました。
泊まれる銀行建築「TOYOOKA1925」の体験

兵庫県豊岡市にある「TOYOOKA1925」は、かつて銀行として使われていた建物を改装した宿泊施設です。1930年代に建てられた旧兵庫県農工銀行豊岡支店を活用し、現在は6室限定のブティックホテルとして営業しています。クラシックな外観と重厚な造りをそのまま残しながら、宿泊者が快適に過ごせるよう工夫が施されています。
建物は近代建築の名手である渡邊節によって設計され、ルネッサンスやアールデコの意匠が取り入れられています。吹き抜けのロビーは銀行時代の窓口があった場所で、現在も開放的な空間として利用されています。クラシックな窓や重厚な柱が残されており、宿泊者はまるで銀行のロビーにいるような感覚を味わえます。
客室はシンプルながらも当時の趣を感じさせる造りで、テレビや時計を置かず「静」を楽しむ空間として整えられています。宿泊者専用のラウンジでは、地元のコーヒーやウイスキーなどを自由に楽しむことができ、建物の雰囲気とともにゆったりとした時間を過ごせます。朝食は地元の食材を使った洋食セットが提供され、建物の歴史と地域文化を同時に体験できる仕組みになっています。
吉宮晴紀はこの宿に宿泊し、スケッチで建物の特徴を記録しました。銀行建築を宿泊施設として活用する事例は珍しく、文化財を保存しながら新しい形で利用する可能性を示すものです。スケッチには吹き抜けの構造や客室の配置が描かれ、建築的な視点から建物の魅力を伝えています。
「TOYOOKA1925」は、地域の交流拠点としても活用されており、イベントや展示会の会場として利用されることもあります。宿泊だけでなく、地域文化を発信する場としての役割も担っている点が特徴です。銀行建築という特異な歴史を持つ建物を宿泊施設として再生したこの事例は、文化財の保存と活用を両立させる象徴的な存在となっています。
読売新聞や中日新聞での書評掲載
吉宮晴紀の著書『ときを感じる お宿図鑑』は、読売新聞や中日新聞などの全国紙でも取り上げられました。新聞での紹介は、専門的な建築分野に関心を持つ人だけでなく、幅広い読者層に活動を届ける大きなきっかけとなりました。
記事では、宿泊施設をスケッチで記録するユニークな手法が注目されました。建築学の専門性を持ちながらも、図や文章を通じて一般の読者にも理解しやすく伝えている点が評価されています。文化財宿を「泊まれる場所」として紹介する視点は、従来の観光案内や建築書籍には少ない切り口であり、新聞の読者に新鮮な印象を与えました。
読売新聞では、文化財宿を巡る旅を通じて建築の魅力を広める活動として紹介され、スケッチの精密さと温かみのある表現が取り上げられました。中日新聞でも、著書が「建築を学ぶ学生ならではの視点でまとめられている」として評価され、専門性と親しみやすさを兼ね備えた内容であることが強調されました。
新聞での書評掲載は、学術的な研究成果を社会に広める役割を果たすと同時に、文化財宿の保存と活用を支援する活動を後押しするものとなりました。専門的な知識を持たない読者にとっても、スケッチを通じて建物の特徴を理解できる点が魅力となり、文化財宿への関心を高める効果を生んでいます。
日本温泉協会誌への寄稿活動
吉宮晴紀は、日本温泉協会が発行する機関誌にも寄稿し、温泉と宿泊施設の建築的価値を伝える活動を行っています。温泉地に残る宿泊施設は、単なる観光資源ではなく、地域の歴史や文化を映し出す建築物でもあります。吉宮は建築学生としての視点を活かし、温泉宿の構造や空間の成り立ちをスケッチや文章で紹介し、専門的な場においてもその価値を広めています。
寄稿では、温泉宿の建築的特徴を具体的に取り上げています。例えば、木造建築の梁や柱の組み方、増築を重ねて複雑になった間取り、浴場の配置など、温泉宿ならではの空間構成を解説しています。温泉は地域の生活文化と密接に結びついており、宿泊施設の建築を理解することは温泉文化そのものを理解することにつながります。
また、温泉宿は長い年月を経て改修や増築を繰り返してきたため、建物の断面を描くことでその歴史を読み解くことができます。吉宮のスケッチは、温泉宿の空間を視覚的に示すだけでなく、建物がどのように人々の暮らしに寄り添ってきたかを伝える役割を果たしています。こうした寄稿は、温泉業界の関係者にとっても、建築的な視点から宿泊施設を見直すきっかけとなっています。
温泉協会誌への寄稿は、一般の読者向けの活動とは異なり、専門的な場での発信です。建築学の知識を持つ研究者として、温泉宿の保存と活用を両立させる重要性を伝える場となっています。文化財宿を支援する活動の一環として、温泉宿の建築的価値を広める取り組みは、学術的な探究心と社会的な使命感を結びつけるものです。
レトロ建築を巡る全国的な情報発信
吉宮晴紀は、全国各地のレトロ建築を巡りながら情報発信を続けています。活動の中心には「泊まれる文化財」というテーマがあり、宿泊体験を通じて建物の価値を伝えることを目的としています。古い宿や歴史的建造物を訪ね、その構造や空間の特徴をスケッチで記録し、SNSや情報サイト「ときやど」で発信しています。
これまでに訪れた宿は100軒以上に及び、東北から九州・沖縄まで幅広い地域を対象としています。例えば、江戸時代から続く北温泉旅館や、明治期の町家を活用した宿、さらには東京ステーションホテルのような近代建築まで、多様な建物を取り上げています。こうした活動は、単なる旅行記ではなく、建築学の視点を加えた文化的な記録として位置づけられています。
情報発信の方法は多岐にわたり、SNSでのスケッチ投稿、情報サイトでの宿データベース化、著書『ときを感じる お宿図鑑』の出版などがあります。スケッチは間取りや断面を描くことで、写真では伝わりにくい建物の内部構造を示し、読者に新しい理解を提供しています。これにより、建築に詳しくない人でも建物の特徴を直感的に感じ取ることができます。
また、吉宮は全国紙やテレビ番組でも取り上げられ、活動が広く知られるようになりました。新聞の書評では専門性と親しみやすさが評価され、テレビ出演では文化財宿の魅力が紹介されました。こうしたメディア露出は、レトロ建築を巡る活動を全国的に広げる大きな後押しとなっています。
全国的な情報発信を通じて、文化財宿は「保存するもの」から「体験できるもの」へと認識が変わりつつあります。吉宮の活動は、建築と旅を結びつける新しい視点を提供し、文化財の保存と活用を両立させる可能性を示しています。
吉宮晴紀って何者?経歴や活動全体を振り返るまとめ
- 千葉大学大学院で建築学を専攻し文化財宿を研究している
- 神奈川県小田原市で育ち幼少期から建築に関心を持った
- 400回以上の宿泊経験を積み建物の空間を体感的に理解した
- 宿泊施設の間取りや断面をスケッチで記録し建築的特徴を示した
- 全国の古い宿を巡り旅と建築研究を結びつけて活動を広げた
- 大学院を一時休学し著書出版の準備に専念した経緯がある
- SNSで「建築学生の呟き」として情報発信を続けている
- 文化財宿の保存と活用を支援する思いが活動の原点となった
- 情報サイト「ときやど」を立ち上げ文化財宿を体系的に紹介した
- 著書『ときを感じる お宿図鑑』で全国の宿をスケッチと写真で紹介した
- 「マツコの知らない世界」に出演し文化財宿の価値を伝えた
- NHKの番組でも取り上げられ活動が全国的に注目された
- 銀行建築を改装した宿「TOYOOKA1925」に宿泊し記録を残した
- 読売新聞や中日新聞で書評が掲載され幅広い読者に届いた
- 日本温泉協会誌に寄稿し温泉宿の建築的価値を専門的に伝えた
- レトロ建築を巡る活動を全国に広げ情報発信を続けている
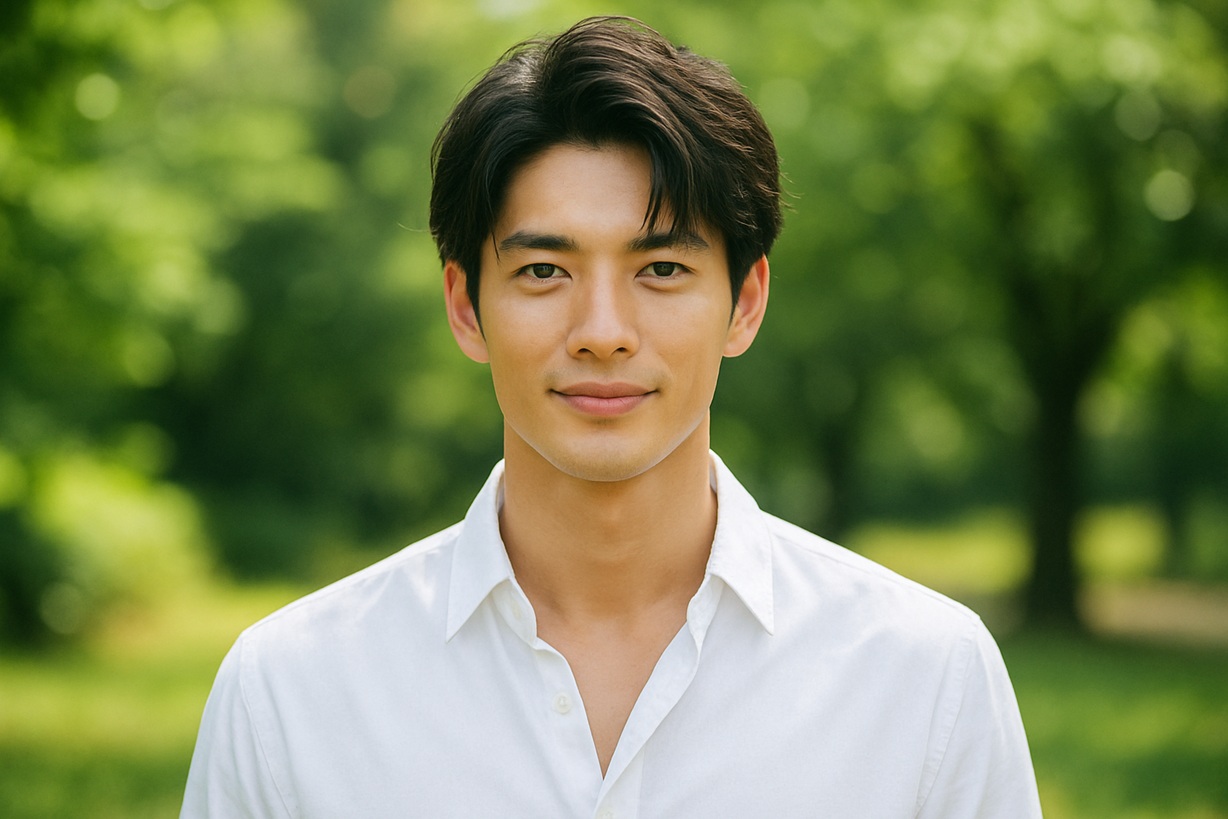


コメント