防衛大学校から航空自衛隊、そしてJAXA宇宙飛行士へと歩んだ油井亀美也の経歴は、日本の宇宙開発に新たな可能性を示すものです。戦闘機パイロットやテストパイロットとしての経験を経て、国際宇宙ステーションでの長期滞在を成功させた彼の挑戦は、多くの人々に夢と希望を与えました。
さらに2025年には再びISSへ向かい、二度目の長期滞在を開始しました。これまでの歩みと今後の展望を知ることで、宇宙開発の未来がより鮮明に見えてきます。続きでは彼の挑戦の軌跡を詳しく紹介します。
【この記事のポイント】
- 防衛大学校から航空自衛隊を経て宇宙飛行士となった歩み
- ISS滞在中に成功させた「こうのとり」キャプチャの成果
- 国際的な研究活動や科学実験に取り組んだ実績
- 2025年クルードラゴンでの再度の長期滞在と今後の展望
▶▶ 油井亀美也さんに関する書籍をアマゾンでチェックしてみる
油井亀美也って何者?防衛大学校から宇宙への経歴
長野県川上村での幼少期と星空体験
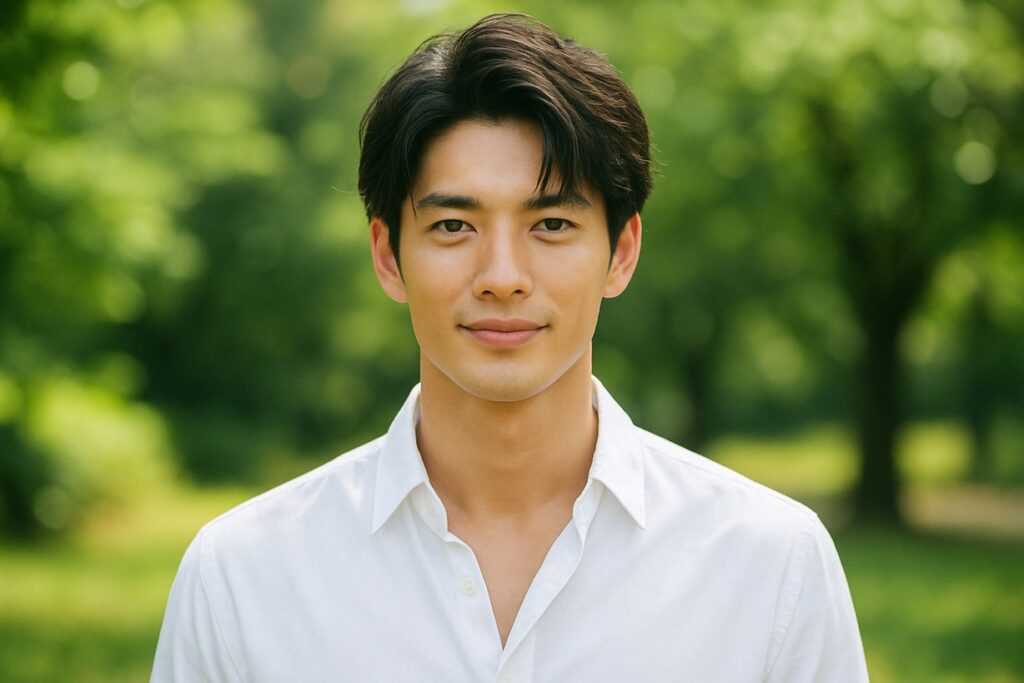
長野県南佐久郡川上村で生まれ育った油井亀美也は、標高が高く澄んだ空気に包まれた環境で幼少期を過ごしました。川上村は野辺山高原に近く、国立天文台野辺山宇宙電波観測所がある地域としても知られています。
夜になると満天の星が広がり、都会では見ることのできないほど鮮明な天の川や星座が姿を現します。そうした自然環境は、子ども時代の油井にとって日常の風景であり、宇宙への関心を芽生えさせる大きな要因となりました。
地元の小学校や中学校に通いながら、地域の人々とともに自然に囲まれた生活を送りました。村の暮らしは農業が中心で、四季折々の風景が身近にありました。冬には澄んだ空気の中で星が一層輝き、夏には高原の涼しさの中で夜空を見上げることができました。こうした環境で育った経験は、後に宇宙飛行士としての活動においても「星を見上げることから始まった夢」として語られることがあります。
川上村では現在も、油井亀美也が宇宙で活動する際に地元の子どもたちと交信イベントが行われています。村民や学生が集まり、宇宙からの声を聞く体験は、地域にとって誇りであり、次世代に夢をつなぐ機会となっています。幼少期に星空を見上げた経験が、今度は地元の子どもたちに新しい夢を与える循環を生み出しています。
防衛大学校理工学専攻での学びと卒業
防衛大学校に進学した油井亀美也は、理工学専攻で航空工学や物理学を中心に学びました。防衛大学校は将来の自衛官を育成するための教育機関であり、学問だけでなく規律や体力面でも厳しい訓練が課されます。油井はその環境で、理論と実践を両立させながら知識を積み重ねていきました。
在学中には儀仗隊に所属し、式典や行事での活動を通じて組織の一員としての責任感を養いました。学業と訓練を並行してこなす生活は容易ではありませんが、そこで培われた忍耐力や集中力は後の航空自衛隊での任務、さらには宇宙飛行士としての活動にもつながる基盤となりました。
1992年に第36期生として卒業した油井は、理工学専攻で得た知識を活かし、航空自衛隊に入隊しました。卒業時点で既に航空工学や物理学の理解を深めていたことは、戦闘機パイロットとしての技術習得に大きな助けとなりました。防衛大学校での経験は、学問と規律を両立させる力を育み、宇宙飛行士として必要な幅広い素養を備える土台となったのです。
航空自衛隊入隊とF-15戦闘機パイロットとしての任務
防衛大学校を卒業した油井亀美也は、航空自衛隊に入隊し、F-15戦闘機のパイロットとして任務に就きました。F-15は日本の防空を担う主力戦闘機であり、その操縦には高度な技術と冷静な判断力が不可欠です。油井は厳しい訓練を経て、実戦さながらの環境で操縦経験を積み重ねました。
パイロットとしての任務は、単に飛行技術を磨くだけではなく、緊急時の対応力や仲間との連携も求められます。空中での複雑な状況に対応するためには、瞬時の判断と確実な操作が必要であり、油井はその中で冷静さと集中力を養いました。
さらに、彼は限られた人材しか選ばれないテストパイロットとしても活躍しました。新しい機体や装備の性能を確認する役割は、危険を伴う一方で、航空技術の発展に直結する重要な任務です。多様な機体に搭乗し、試験飛行を重ねることで、幅広い知識と経験を得ました。
航空自衛隊での生活は、日々の訓練や任務を通じて心身を鍛える場でもありました。厳しい環境を乗り越えることで、油井は人間的にも成長し、後に宇宙飛行士として挑戦する際の大きな支えとなりました。戦闘機パイロットとして培った冷静さと技術力は、宇宙での活動においても欠かせない資質となっています。
テストパイロットとしての高度な飛行経験
戦闘機パイロットとしての任務を重ねた油井亀美也は、限られた人材しか選ばれないテストパイロットの道へ進みました。テストパイロットは、新型機や改修機の性能を確認し、安全性を評価する重要な役割を担います。通常の飛行任務とは異なり、未知の挙動に直面する可能性が高く、冷静な判断力と豊富な知識が求められます。
油井は航空自衛隊で培った操縦技術を基盤に、試験飛行で多様な機体を操縦しました。新しい機体の限界性能を探る飛行は危険を伴いますが、航空技術の発展には欠かせない作業です。飛行中の細かな挙動や機体の反応を記録し、設計や改良に役立てることが求められました。こうした経験は、単なる操縦技術だけでなく、分析力や問題解決能力を磨く場でもありました。
テストパイロットとしての活動は、宇宙飛行士としての資質にも直結しました。未知の環境に挑む姿勢や、極限状況で冷静に対応する力は、宇宙での任務に必要不可欠です。油井が後に宇宙飛行士として選抜された背景には、この段階で培った幅広い飛行経験と技術的な信頼性が大きく影響しています。
航空自衛隊でのテストパイロット経験は、油井亀美也の経歴の中でも特に重要な位置を占めています。危険を伴う任務を通じて得た知識と実践力は、彼を宇宙へと導く確かな基盤となりました。
航空幕僚監部勤務と幹部学校での指揮幕僚課程

戦闘機パイロットやテストパイロットとしての経験を積んだ油井亀美也は、航空自衛隊幹部学校で指揮幕僚課程を修了しました。この課程は、航空自衛隊の幹部候補が組織運営や戦略的思考を学ぶための教育機関であり、部隊を率いるための知識と判断力を養う場です。ここで油井は、戦術や作戦立案、組織管理に関する体系的な教育を受けました。
指揮幕僚課程では、単なる操縦技術だけではなく、組織全体を俯瞰する視点が求められます。部隊の運営や戦略的な意思決定を行うためには、幅広い知識と冷静な分析力が必要です。油井はこの課程を通じて、リーダーシップをさらに磨き、仲間を導く力を高めました。
課程修了後は航空幕僚監部に勤務し、防衛課での業務に携わりました。航空幕僚監部は航空自衛隊の中枢であり、政策立案や防衛計画の策定を担う重要な組織です。ここでの勤務は、現場で培った経験を組織運営や戦略に結びつける役割を果たしました。実際の飛行任務から一歩離れ、国防全体を見渡す立場で働くことは、油井にとって新たな視野を広げる機会となりました。
この時期に培った組織的な視点や戦略的思考は、後に宇宙飛行士として国際的なチームで活動する際にも活かされています。宇宙での任務は多国籍の仲間と協力しながら進められるため、リーダーシップや調整力が不可欠です。航空幕僚監部での経験は、宇宙飛行士としての活動に直結する重要な経歴の一部となっています。
2009年JAXA宇宙飛行士候補者に選抜
2009年、油井亀美也はJAXAの宇宙飛行士候補者として選抜されました。この選抜は、日本の宇宙開発において重要な節目であり、彼は自衛官出身者として初めて宇宙飛行士候補に加わった人物となりました。航空自衛隊で培った操縦技術や冷静な判断力、さらにテストパイロットとしての経験が評価され、厳しい選考を突破しました。
選抜試験は、身体的な適性だけでなく、心理的な安定性や国際的な協調性も問われる内容でした。宇宙飛行士は長期間にわたり閉鎖的な環境で生活するため、仲間との協力やストレス耐性が欠かせません。油井は自衛隊での経験を活かし、規律を守りながらも柔軟に対応できる資質を示しました。
候補者に選ばれた後は、ロシア語の習得や宇宙医学の基礎、サバイバル技術など幅広い分野の訓練に取り組みました。宇宙飛行士として必要な知識は多岐にわたり、地上での準備段階から国際的な活動を視野に入れた教育が行われました。油井はその過程で、技術者としての能力だけでなく、国際的なチームの一員として活動するための協調性を磨いていきました。
この選抜を経て、油井亀美也は日本の宇宙開発に新しい人材として加わり、後の国際宇宙ステーションでの長期滞在へとつながる道を歩み始めました。自衛官としての経歴と宇宙飛行士としての挑戦が結びついた瞬間であり、彼の人生における大きな転機となった出来事でした。
自衛官出身初の宇宙飛行士訓練生としての挑戦
2009年に宇宙飛行士候補者として選抜された油井亀美也は、航空自衛官出身者として初めて宇宙飛行士訓練生となりました。選抜後はJAXAでの基礎訓練に臨み、宇宙飛行士として必要な幅広い知識と技能を身につけていきました。
訓練では、国際宇宙ステーションでの活動を想定し、ロシア語の習得が必須とされました。ソユーズ宇宙船の運用やロシアの管制とのやり取りに対応するため、語学力は欠かせない要素です。油井は日々の学習を通じて、専門的な技術用語を含む会話能力を高めていきました。
また、宇宙医学の基礎も学びました。宇宙環境では微小重力による筋力低下や骨密度の減少など、地上では起こりにくい身体的変化が生じます。訓練ではこうした影響を理解し、健康を維持するための知識を習得しました。さらに、緊急時に備えた医学的対応力も求められました。
サバイバル技術の習得も重要な課題でした。宇宙船が不測の事態で地球の僻地に着陸した場合に備え、極寒地や森林などさまざまな環境で生き延びるための訓練が行われました。自衛官として培った規律や体力は、このような過酷な状況での適応力に直結しました。
基礎訓練を経て、2011年にはすべての課程を修了し、正式に宇宙飛行士として認定されました。自衛官出身ならではの経験と精神力は、宇宙飛行士としての活動に大きな強みとなり、国際的なチームの中でも信頼される存在へと成長していきました。
基礎訓練修了と正式認定までの過程
油井亀美也は2009年に宇宙飛行士候補者として選抜され、国際宇宙ステーション搭乗を目指す基礎訓練に参加しました。この訓練は、日本を含むISS参加各国が合意した計画に基づいて行われ、宇宙飛行士として必要な知識や技能を幅広く身につけることを目的としています。
訓練では、宇宙機システムやISSの構造に関する学習、船外活動のための技術習得、ロボットアーム操作などの実践的な課題が含まれていました。さらに、航空機操縦訓練やサバイバル訓練も行われ、極限環境での対応力を養うことが求められました。語学面では英語とロシア語の習得が必須であり、国際的なチームで活動するための基盤を築きました。
数年にわたる厳しい訓練を経て、2011年7月にすべての基礎訓練項目を修了し、正式に宇宙飛行士として認定されました。この認定は、油井が宇宙飛行士として国際的な任務に参加できる資格を得たことを意味します。認定後はNASAジョンソン宇宙センターを拠点に、さらに高度な訓練を積みながら、将来の宇宙飛行に備える活動を続けました。
防衛大学校から航空自衛隊、そして宇宙飛行士へと至る道のりは、日本の宇宙開発に新たな人材を加えるものとなりました。自衛官として培った規律や冷静な判断力は、宇宙飛行士としての活動においても大きな強みとなり、国際的な舞台で活躍するための確かな基盤となったのです。
▶▶ 油井亀美也さんに関する書籍をアマゾンでチェックしてみる
油井亀美也って何者?経歴とISS長期滞在の実績
ISS第44次/第45次長期滞在クルーとしての任務

2015年7月、油井亀美也はソユーズTMA-17M宇宙船に搭乗し、国際宇宙ステーション第44次/第45次長期滞在クルーの一員として宇宙へ向かいました。約142日間にわたる滞在は、彼にとって初めての宇宙生活であり、日本の宇宙飛行士としても重要な節目となりました。
滞在中はフライトエンジニアとして活動し、日本の「きぼう」実験棟を含むステーション全体のシステム運用を担当しました。生命維持装置や電力供給など、ISSの安定した運用を支える役割を果たしながら、国際的な研究活動にも積極的に参加しました。科学実験では、微小重力環境を利用した医学や材料科学の研究を進め、地上の技術や医療に応用可能な成果を積み上げました。
また、日本の宇宙ステーション補給機「こうのとり」5号機のキャプチャ作業を成功させたことは大きな成果のひとつです。ロボットアームを操作して補給機を捕捉する作業は高度な技術を要し、国際的にも注目されました。これにより、食料や実験機材などの補給が円滑に行われ、ステーションでの活動が支えられました。
滞在中には教育活動にも力を入れ、地上の子どもたちと交信イベントを行いました。宇宙からの声を届けることで、次世代に夢を与える取り組みとなり、地域や学校で大きな話題を呼びました。さらに、SNSを通じて宇宙から撮影した地球の写真を発信し、多くの人々に宇宙の魅力を伝えました。
2015年12月、ソユーズ宇宙船で地球へ帰還し、約4か月にわたる任務を終えました。この経験は油井にとって大きな財産となり、後の再飛行や国際的な宇宙活動に向けた基盤を築くものとなりました。
ソユーズTMA-17Mでの打ち上げと滞在
2015年7月22日、油井亀美也はソユーズTMA-17M宇宙船に搭乗し、国際宇宙ステーションへ向けて打ち上げられました。打ち上げはカザフスタンのバイコヌール宇宙基地から行われ、ロシアの宇宙飛行士オレッグ・コノネンコ、NASAの宇宙飛行士チェル・リンドグレンとともに乗組員として参加しました。三人は国際的なチームの一員として、ISSでの長期滞在任務を開始しました。
打ち上げ直後には太陽電池パネルの展開に不具合が発生しましたが、ISSへの到着後に修復され、任務は予定通り進められました。ISSに到着した油井は、フライトエンジニアとしてステーションの運用や科学実験に携わり、日本の「きぼう」実験棟を含む設備の管理を担当しました。滞在中には補給機「こうのとり」5号機のキャプチャ作業を成功させ、国際的な協力の中で日本の技術力を示す成果を残しました。
宇宙での生活は約4か月に及び、微小重力環境での科学研究や医学実験、教育活動など幅広い任務を遂行しました。地上の子どもたちとの交信イベントやSNSを通じた情報発信も行い、宇宙からの視点を多くの人々に届けました。
2015年12月11日、ソユーズTMA-17Mで地球へ帰還し、カザフスタンに着陸しました。打ち上げから帰還までの過程は、国際的な協力の象徴であり、油井亀美也にとって初めての宇宙滞在を成功裏に終えるものとなりました。この経験は、後の再飛行や国際的な宇宙活動に向けた大きな基盤となりました。
「こうのとり」5号機キャプチャの成功
2015年8月24日、日本の宇宙ステーション補給機「こうのとり」5号機は国際宇宙ステーションに到着しました。油井亀美也はロボットアームを操作し、約10メートルまで接近した補給機を慎重に把持しました。この作業は「キャプチャ」と呼ばれ、ISSの運用において最も緊張感の高い場面のひとつです。成功した瞬間、筑波宇宙センターの管制室では大きな拍手が沸き起こり、日本の宇宙技術が国際的に評価される出来事となりました。
「こうのとり」5号機には、宇宙飛行士の生活に必要な水や食料、衣類のほか、科学実験に用いる装置など約5.5トンの物資が積み込まれていました。補給船の到着は、ISSでの長期滞在を支えるために欠かせないものであり、特にこの時期は他国の補給船の打ち上げ失敗が続いていたため、世界中から注目されていました。日本の補給機が確実に物資を届けたことは、国際的な宇宙活動における信頼性を示すものとなりました。
キャプチャ作業は油井亀美也にとっても大きな挑戦でした。ロボットアームの操作は高い集中力と精密な技術を必要とし、わずかな誤差が大きな結果を招く可能性があります。成功後、油井は「こうのとり」を金色の宝箱のようだと表現し、その瞬間を誇りに感じたと語りました。日本人宇宙飛行士が直接ロボットアームを操作して補給機を捕捉したのは初めてであり、歴史的な意義を持つ出来事でした。
この成功は、日本の宇宙開発が国際的な協力の中で重要な役割を果たしていることを示しました。補給機の確実な運用は、ISSでの研究や生活を支える基盤であり、今後の宇宙探査にもつながる成果です。油井亀美也の冷静な判断と技術力は、日本の宇宙飛行士の存在感を世界に示すものとなりました。
NEEMO16海底訓練やNOLS野外リーダーシップ訓練
油井亀美也は宇宙飛行士としての準備過程で、地上では得られない極限環境での適応力を養うために、海底や野外での特別な訓練に参加しました。その代表的なものが、アメリカ・フロリダ州沖の海底で行われたNEEMO16訓練と、自然環境を舞台にしたNOLS野外リーダーシップ訓練です。
NEEMO16は「NASA Extreme Environment Mission Operations」の略で、海底に設置された居住施設「アクエリアス」で行われました。ここでは宇宙での生活を模した閉鎖環境に滞在し、船外活動に相当する水中作業を行います。油井は国際的なチームの一員として参加し、限られた空間での共同生活や、緊急時の対応を含む多様な課題に取り組みました。水中での作業は宇宙服を着て行う船外活動に近い感覚を再現できるため、宇宙飛行士にとって重要な訓練となります。
一方、NOLS(National Outdoor Leadership School)での訓練は、自然環境の中でリーダーシップを発揮する力を磨くことを目的としています。油井は仲間とともに野外での長期生活を経験し、限られた資源を活用しながらチームをまとめる力を養いました。天候の変化や予測不能な状況に対応する過程で、柔軟な判断力や協調性を高めることができました。
これらの訓練は、宇宙飛行士としての技術的な能力だけでなく、人間関係や心理的な適応力を育てる場でもありました。閉鎖的な環境や過酷な自然条件での経験は、国際宇宙ステーションでの長期滞在に直結する重要な準備となり、油井亀美也が宇宙で冷静に任務を遂行するための基盤を築いたのです。
滞在中の科学実験・医学実験の取り組み

油井亀美也が国際宇宙ステーションに滞在した期間中、微小重力環境を活かした多様な科学実験や医学研究が行われました。ISSは地上では再現できない環境を提供するため、宇宙飛行士は日々分刻みのスケジュールで研究活動に取り組みます。
植物の成長に関する研究では、細胞分裂が重力の影響をどのように受けるかを観察しました。特に細胞分裂時に形成される微小管構造に注目し、蛍光顕微鏡を用いたリアルタイム観察や遺伝子発現の解析が行われました。これにより、植物が重力の少ない環境でどのように成長するかを理解する手がかりが得られ、将来の長期宇宙滞在や月面探査での食料生産に役立つ可能性が示されました。
火災安全に関する実験も重要なテーマでした。微小重力下では炎の形や燃焼の仕方が地上と大きく異なるため、燃焼実験を通じて宇宙での火災防止基準を検証しました。これは宇宙船の安全性を高めるだけでなく、地上の防火技術にも応用できる成果です。
医学分野では、宇宙環境が人体に与える影響を調べる研究が進められました。微小重力下では筋力や骨密度が低下しやすいため、運動プログラムや栄養管理の効果を検証しました。さらに、血液や細胞の変化を分析することで、長期滞在に伴う健康リスクを軽減する方法を探りました。
油井は日本の「きぼう」実験棟を拠点に、国際的な研究チームと協力しながらこれらの実験を遂行しました。成果は宇宙探査の未来に直結するだけでなく、地上の科学技術や医療の発展にもつながっています。宇宙で得られた知見が、私たちの生活をより豊かにする研究へと還元されているのです。
国際パートナーとの協力による成果
油井亀美也が国際宇宙ステーションに滞在した期間中、活動は常に多国籍チームとの協力によって進められました。ISSはアメリカ、ロシア、ヨーロッパ、日本、カナダといった複数の宇宙機関が共同で運用しており、日々の任務は国際的な連携の上に成り立っています。油井はその一員として、各国の宇宙飛行士と共に研究や設備の維持管理を行いました。
科学実験では、アメリカのNASAが主導する医学研究や、ヨーロッパ宇宙機関による材料科学の実験に参加しました。微小重力環境での成果は、地上の医療や産業にも応用可能であり、国際的な研究協力の意義を示すものとなりました。ロシアの宇宙船ソユーズを利用した打ち上げや帰還も、国際協力の象徴的な場面であり、異なる国の技術が一つの目標に向かって結集していることを実感させるものでした。
また、補給船の運用や船外活動においても国際的な役割分担がありました。日本の「こうのとり」補給機のキャプチャ作業は油井が担当しましたが、その後の物資移送やステーション内での利用は各国のクルーが協力して進めました。こうした共同作業は、宇宙での生活を支える基盤であり、国際的な信頼関係を深める機会となりました。
教育活動や広報活動でも国際的な協力が見られました。油井は日本の子どもたちとの交信イベントを行う一方で、他国の宇宙飛行士と共に地球の写真を発信し、世界中の人々に宇宙の姿を届けました。国境を越えた活動は、宇宙開発が人類全体の挑戦であることを示しています。
このような国際パートナーとの協力は、単なる技術的な連携にとどまらず、文化や価値観の交流を伴うものでした。油井亀美也の滞在は、宇宙開発の未来が多国籍の協力によって広がっていくことを示す象徴的な経験となりました。
2025年クルードラゴンでの再度のISS滞在
2025年8月、油井亀美也はスペースXのクルードラゴン宇宙船「Crew-11」に搭乗し、再び国際宇宙ステーションへ向かいました。2015年以来、約10年ぶりとなる宇宙飛行であり、日本人宇宙飛行士として二度目の長期滞在に挑むことになりました。打ち上げはフロリダ州ケネディ宇宙センターから行われ、NASAやロシアの宇宙飛行士とともに国際的なチームの一員として参加しました。
打ち上げは日本時間8月2日未明に行われ、約15時間後にISSへドッキングしました。到着後、油井は第73次/第74次長期滞在クルーの一員として活動を開始しました。ISSではすでに大西卓哉宇宙飛行士が滞在しており、二人の日本人宇宙飛行士が同時にステーションで活動するという貴重な機会となりました。再会の場面は国際的にも注目され、宇宙での協力の象徴として多くの人々に伝えられました。
今回の滞在は約半年間に及ぶ予定で、生命科学や物質科学の研究に加え、将来の有人探査に向けた技術実証が行われます。特に二酸化炭素除去技術の検証や、次世代教育プログラムとして「きぼう」ロボットプログラミング競技会やアジアントライゼロGといった活動も予定されています。これらは宇宙での生活を支える技術の発展だけでなく、地上の子どもたちに夢を届ける取り組みでもあります。
油井は到着直後に「10年ぶりに宇宙に帰ってきました」と語り、日本の存在を世界に示す意気込みを表しました。国際的なチームの中で日本人宇宙飛行士が果たす役割は大きく、ISSでの活動は今後の月探査やアルテミス計画へとつながる重要な経験となります。二度目の長期滞在は、彼自身の経験の蓄積だけでなく、日本の宇宙開発にとっても新たな一歩となりました。
宇宙飛行士としての今後の展望
油井亀美也は、二度目の国際宇宙ステーション滞在を経て、今後も宇宙飛行士としての活動を続けることが期待されています。ISSは2030年頃に退役を迎える予定であり、その後は商業宇宙ステーションの時代へ移行すると見られています。油井の経験は、この過渡期において日本の宇宙開発を国際的に結びつける重要な役割を果たすものです。
ISSでの活動を通じて培った技術や知識は、次世代の有人探査計画に直結します。特に月探査やアルテミス計画への参加が視野に入っており、油井はその経験を活かして日本の宇宙飛行士が国際的な探査活動に貢献する道を広げています。宇宙での長期滞在技術や生命維持システムの運用経験は、将来の深宇宙探査に不可欠な要素です。
また、教育や広報活動にも積極的に関わる姿勢が見られます。宇宙からの写真や体験を発信することで、次世代に夢を届ける活動を続けています。特に子どもたちとの交信イベントやSNSでの情報発信は、宇宙開発を身近に感じさせる取り組みとして評価されています。こうした活動は、後進の育成や宇宙分野への関心を広げる大きな力となっています。
さらに、油井は「恩返し」という言葉を使い、これまで支えてくれた人々や社会に対して、自らの経験を還元したいという思いを語っています。二度目の宇宙滞在では、余裕を持って活動できる部分を活かし、教育や研究支援に力を注ぐ意欲を示しています。これは、単なる宇宙飛行士としての任務にとどまらず、日本の宇宙開発全体を支える姿勢につながっています。
今後は、ISSでの活動を基盤に、商業宇宙ステーションや月探査計画への参加が期待されます。油井亀美也は、経験豊富な人材として後進の育成に関わりながら、日本の宇宙開発を国際的な舞台でさらに前進させる存在となるでしょう。
油井亀美也って何者?経歴から見える歩みの総括
- 長野県川上村で育ち星空に親しんだ幼少期の経験が宇宙への関心を育んだ
- 防衛大学校理工学専攻で学び航空工学や物理学を修めたことが基盤となった
- 航空自衛隊に入隊しF15戦闘機パイロットとして高度な操縦技術を習得した
- テストパイロットとして新型機の評価や安全性確認に携わり経験を積んだ
- 航空幕僚監部勤務や幹部学校で指揮幕僚課程を修了し戦略的思考を磨いた
- 2009年にJAXA宇宙飛行士候補者に選抜され自衛官出身初の挑戦となった
- 訓練ではロシア語や宇宙医学サバイバル技術など幅広い分野を習得した
- 数年に及ぶ基礎訓練を経て2011年に正式に宇宙飛行士として認定された
- 2015年ソユーズTMA17Mで打ち上げられISS第44次第45次長期滞在を実施した
- 滞在中に日本の補給機こうのとり5号機キャプチャを成功させた実績がある
- NEEMO16海底訓練やNOLS野外リーダーシップ訓練で極限環境適応力を養った
- 微小重力環境を活かした科学実験や医学研究に取り組み成果を地上へ還元した
- アメリカロシアヨーロッパなど国際パートナーと協力し研究活動を推進した
- 2025年クルードラゴンCrew11で再びISSへ向かい二度目の長期滞在を開始した
- 今後も宇宙飛行士として活動を続け日本の宇宙開発と後進育成に貢献が期待される
▶▶ 油井亀美也さんに関する書籍をアマゾンでチェックしてみる
▶▶ あわせてこちらの記事もどうぞ




コメント