岩崎う大さんは、お笑い、演劇、漫画、批評といった複数のジャンルを横断しながら、独自の物語を描き続けている表現者です。2013年に「キングオブコント」で優勝したお笑いコンビ「かもめんたる」の活動をはじめ、演劇では岸田國士戯曲賞の候補に選ばれるなど、各分野で高い評価を得ています。
彼の作品には、笑いの中に潜む違和感や静けさ、そして人間の複雑な感情が丁寧に織り込まれており、観客や読者に深い余韻を残します。ジャンルの枠にとらわれることなく、物語の構造と人物描写にこだわる姿勢は、岩崎さんならではの魅力です。
本記事では、岩崎う大さんの幼少期から現在に至るまでの活動を時系列で整理しながら、彼がどのようにしてジャンルを超えた表現者となったのか、その創作の背景と魅力に迫っていきます。
【この記事のポイント】
- 岩崎う大の経歴と活動の流れを時系列で整理
- コントや演劇における構成力と人物描写の特徴
- 漫画や批評活動に見られる表現の一貫性
- 若手芸人育成や朝ドラ出演など現在の活躍
岩崎う大の経歴と活動を時系列で整理
幼少期からオーストラリアでの生活
岩崎う大は東京都西東京市で生まれ、幼稚園から小学校5年生までは湘南で過ごしていた。中学3年の途中から高校卒業までは、親の意向でオーストラリアのパースという都市に移り住み、現地の高校に通っていた。英語環境での生活は、当初は期待と不安が入り混じるものだったが、実際には言語の壁や文化の違いに戸惑う日々が続いた。
日本のテレビ番組が見られなくなったことは、彼にとって大きな喪失感だった。特に『ダウンタウンのごっつええ感じ』などのお笑い番組に強く影響を受けていたため、それらに触れられないことが孤独感を深めた。現地の日本食店が貸し出していたVHSで過去の番組を繰り返し観ることで、心の拠り所を見つけていたという。
英語での授業に苦労しながらも、異文化の中で過ごした時間は、彼の感性や表現力に深く影響を与えた。日本のお笑いへの渇望が募る中で、自分も芸人になりたいという思いが芽生えたのは17歳の頃だった。この時期の経験が、後の創作活動において、独特な視点や構成力を育む土壌となっている。
高校時代には人前でネタを披露することはなかったが、弟と漫才の録音をして遊ぶなど、表現への興味は途切れることなく続いていた。帰国後は帰国子女枠で早稲田大学に進学し、演劇サークルで本格的に表現活動を始めることになる。
異国での思春期を過ごした岩崎う大の背景には、言葉や文化の違いを乗り越えながら、自分の内面と向き合った時間がある。その経験が、彼の作品に漂う独自の空気感や、物語の奥行きに繋がっている。
早稲田大学での演劇サークル活動

岩崎う大は早稲田大学政治経済学部に進学し、入学式の日に演劇系お笑いサークル「WAGE」に誘われて参加した。このサークルは「Waseda Academic Gag Essence」の略称で、1990年代後半から早稲田大学内で活動していた。メンバーは数十人規模で、月1回のライブを渋谷で開催するなど、学生芸人の中でも活発なグループだった。
岩崎は当初からプロ志向が強く、サークル内でもネタ作りに熱心に取り組んでいた。小島よしおや槙尾ユウスケらと共に活動し、5人組のコントグループとして「WAGE」の名で芸能活動を開始。2001年には学生芸人の大会で入賞し、芸能事務所に所属するきっかけをつかんだ。
サークル内では、スタイリッシュで構成の緻密なコントを展開していた。集団コントやピン芸など、組み合わせを変えながら多様なスタイルに挑戦し、大学内外で熱狂的なファンを獲得していた。岩崎は脚本を担当し、人物の心理や会話のリアリティを重視した構成を得意としていた。
一方で、岩崎はグループ活動に対して葛藤も抱えていた。自分たちのネタが本当に面白いのかという疑問や、5人という人数が物珍しさで受けているだけではないかという不安があった。ライブでの敗北や方向性の違いが重なり、2006年にグループは解散することになる。
大学時代には、NSC東京にも通いながら外部の芸人とも交流を深めていた。卒業式には出席せず、ライブ活動を優先するほど表現への情熱が強かった。早稲田大学という多様な人材が集まる環境は、岩崎にとって創作の刺激に満ちた場所であり、後の活動の土台となっている。
WAGE時代のコント制作と葛藤
岩崎う大が所属していたコントグループ「WAGE」は、早稲田大学のお笑いサークルから誕生した学生芸人集団で、約10人のメンバーが在籍していた。2001年には「ギャグ大学偏差値2000」で入賞し、芸能事務所に所属するなど、学生芸人としては異例のプロ活動を展開していた。
グループは5人編成で、スタイリッシュかつ構成にこだわったコントを武器に、テレビ番組やライブに出演していた。岩崎は脚本を担当し、物語性や人物の心理描写に力を入れたネタ作りを行っていたが、活動を続ける中で次第に違和感を抱くようになる。
テレビ出演が増えるにつれ、岩崎は「5人という人数の珍しさで呼ばれているだけではないか」「本当に面白いのか」といった疑問を感じるようになった。グループとしての人気が高まる一方で、自分たちの笑いが本質的に評価されているのかという不安が募っていった。
2004年に行われたライブでは、後に「オードリー」となるナイスミドルに敗北し、岩崎はその結果をきっかけに解散を意識し始める。メンバー間でも方向性の違いが顕著になり、脚本家志望、俳優志望、ピン芸人志望など、それぞれが異なる道を模索していた。
事務所との契約が切れるタイミングで、岩崎は活動休止を提案。話し合いの末、2006年3月にグループは解散することとなった。岩崎はその後、槙尾ユウスケと「かもめんたる」を結成し、自らの理想とする表現を追求する道へと進んでいく。
WAGE時代の葛藤は、岩崎にとって表現者としての原点であり、集団の中で自分の声をどう響かせるかという問いと向き合った時間でもあった。その経験が、後の創作活動における構成力や人物描写の深さに繋がっている。
かもめんたる結成とキングオブコント優勝

岩崎う大はWAGE解散後、しばらくピン芸人として活動していたが、2007年に槙尾ユウスケを誘い、演劇ユニット「劇団イワサキマキオ」を立ち上げた。二人は早稲田大学のお笑いサークルで出会って以来の仲で、互いの表現力を信頼し合っていた。演劇公演を重ねる中で、より多くの観客に届ける手段としてコントライブへと活動の軸を移していく。
2009年にはサンミュージックプロダクションに所属し、2010年にコンビ名を「かもめんたる」に改称。演劇的な要素を取り入れたコントを武器に、ライブ活動を精力的に展開した。ネタ作りは岩崎が担当し、槙尾はその世界観を的確に演じることで、二人の表現は独自の深みを持つようになった。
2012年の『キングオブコント』では3位に入賞し、翌2013年には見事優勝を果たす。この大会で披露されたネタは、日常の中に潜む狂気や違和感を巧みに描き出し、観客に強烈な印象を残した。優勝によって一躍注目を集めたが、岩崎は「生身の自分を面白く見せる」ことへの苦手意識が強く、バラエティ番組での立ち回りに悩むこともあった。
テレビ出演が増える一方で、ネタ番組の減少によりコントを披露する場が限られていく中、二人は演劇活動へと再び力を注ぐようになる。2015年には「劇団かもめんたる」を旗揚げし、演劇公演を定期的に開催。その脚本は岸田國士戯曲賞候補にも選ばれるなど、演劇界でも高い評価を受けている。
かもめんたるの活動は、コントと演劇の境界を越えた表現を追求するものであり、ジャンルに縛られない柔軟なスタンスが特徴である。キングオブコント優勝はその転機となり、二人の表現者としての道を大きく広げるきっかけとなった。
劇団かもめんたるでの脚本活動
岩崎う大は2015年に「劇団かもめんたる」を旗揚げし、原作・脚本・演出のすべてを担う中心人物として活動している。お笑いコンビとしての経験を活かしながら、舞台作品ではより深い人間描写と物語構成に力を注いでいる。演劇界では、2020年と2021年に岸田國士戯曲賞の候補作として選ばれ、劇作家としての評価も高まっている。
彼の脚本は、日常の中に潜む違和感や感情の揺れを丁寧に描き出すことに特徴がある。登場人物の関係性や心理の変化を、緻密な構成で浮かび上がらせる手法は、観客に強い印象を残す。笑いを交えながらも、物語の根底には悲劇性や切実さが流れており、単なるコメディとは一線を画している。
舞台上での制約を逆手に取り、観客の想像力を刺激する演出も工夫されている。限られた空間の中で展開される物語は、密室劇のような緊張感を持ちつつ、人物同士の関係性に焦点を当てている。岩崎は、脚本を書くことを「勝負すべき仕事」と位置づけており、ゼロから物語を生み出す苦しさと向き合いながら創作を続けている。
また、映像作品でも脚本を手がけており、Huluオリジナルドラマ『THE LIMIT』では2話分の脚本を担当。舞台と映像の違いを理解しながら、それぞれのメディアに適した表現を模索している。演劇と映像の両方で活躍することで、表現の幅を広げ、観客との新たな接点を築いている。
劇団かもめんたるの作品は、笑いと哀しみが交錯する独自の世界観を持ち、観る者に深い余韻を残す。岩崎の脚本は、ジャンルを超えて人間の本質に迫る力を持っており、今後の展開にも注目が集まっている。
漫画家としての作画と作品評価

岩崎う大は芸人としての活動に加え、漫画家としても本格的に創作を行っている。美術系の教育を受けていた背景があり、画力と構成力の両面で高い水準を持っている。芸人が漫画を描くという枠を超え、表現者としての幅広さを示す活動のひとつとなっている。
代表作のひとつが、芥川賞作家・又吉直樹の小説『火花』の漫画化である。この作品では、原作の持つ文学的な空気感を損なうことなく、登場人物の感情や関係性を繊細に描写している。セリフの間や構図の取り方に演劇的な感覚が活かされており、読者に強い印象を与える構成となっている。
また、自身のオリジナル作品『マイデリケートゾーン』では、下ネタを題材にしながらも人間の内面に迫るような描写が特徴的である。ギャグとヒューマンドラマが融合した作風は、読者から「何度読んでも好きな世界観」と評されるほどの支持を得ている。漫画という媒体でも、岩崎らしい違和感や余韻を残す表現が貫かれている。
SNSでは、自作漫画の一部を公開することもあり、読者との距離感を近づける工夫も見られる。芸人としての知名度を活かしながら、漫画家として独立した評価を得ている点は特筆すべきである。演劇・コント・漫画という異なるジャンルを横断しながら、物語を描く力に一貫性があることが、岩崎う大の創作活動の強みとなっている。
若手芸人への審査・育成活動
岩崎う大は、若手芸人の育成にも積極的に関わっている。代表的な企画が「キングオブう大」で、これはテレビ番組『しくじり先生』の特別企画として始まった賞レースである。若手芸人がコントを披露し、岩崎がその場で採点と批評を行うスタイルが特徴で、視聴者にも芸人にも緊張感と学びをもたらしている。
この企画では、岩崎が100点満点で採点しながら、ネタの構造や演出、キャラクターの説得力などを細かく分析している。単なる感想ではなく、論理的な視点からの評価が中心で、芸人たちはその指摘を真剣に受け止めている。実際に「キングオブう大」で高得点を獲得したコンビが、後に本家『キングオブコント』でも結果を残すなど、育成の場としての機能も果たしている。
岩崎はこの企画を通じて、若手芸人の可能性を引き出すことに力を注いでいる。ネタの中にある「正解」を見つけるような視点で評価を行い、芸人自身が自分の表現を再発見するきっかけを提供している。批評の言葉には厳しさもあるが、そこには作品への深い理解と敬意が込められている。
また、岩崎は『ABCお笑いグランプリ』や『UNDER5 AWARD』など、他の賞レースでも審査員を務めており、若手芸人の登竜門となる舞台で重要な役割を担っている。審査では、笑いの質だけでなく、構成力や演技力、観客との距離感など、多角的な視点から評価を行っている。
このような活動を通じて、岩崎う大は芸人としてだけでなく、批評家・育成者としても信頼を集めている。若手芸人にとっては、彼の言葉が次のステップへのヒントとなり、表現の幅を広げるきっかけとなっている。
岩崎う大の作品と表現手法の特徴とは
コントにおける物語性と余韻

岩崎う大のコントは、単なる笑いを目的としたものではなく、物語としての構造を持ち、観客に余韻を残す作品として成立している。登場人物の関係性や心理の変化を丁寧に描きながら、舞台上で展開される状況には、日常の中に潜む違和感や不穏さが巧みに織り込まれている。
彼の作品では、笑いの中にある「静けさ」や「間」が重要な要素となっている。一つのネタが終わった後に残る感情や、観客が持ち帰る印象までを含めて作品として設計されている。そのため、観客はただ笑うだけでなく、どこか心に引っかかるような感覚を覚えることが多い。
演劇の経験がコントに活かされている点も特徴的である。幕間の演出や構成の工夫により、ネタとネタの間にも物語の流れが感じられるようになっている。映像や音響に頼らず、人間の動きや会話だけで空気を作り出す手法は、舞台芸術としての完成度を高めている。
また、ネタの発想は日常の些細な出来事や人間関係のもつれから生まれることが多く、観客が「あるある」と共感できる一方で、どこか異様な空気感が漂う。その違和感が笑いに転化される瞬間に、岩崎の構成力と演出力が発揮されている。
作品の中には、哲学的な問いかけや、現実と虚構の境界を揺さぶるような要素も含まれている。それらが物語の深みを生み出し、観客にとっては一度観ただけでは終わらない、反芻したくなるような体験となっている。
岩崎う大のコントは、笑いの形式にとどまらず、物語としての完成度を追求する姿勢が貫かれている。その結果、観客の記憶に残る作品として、長く語られる存在となっている。
漫画『火花』の構成力と描写
漫画『火花』は、芥川賞を受賞した又吉直樹の原作小説をもとに、岩崎う大が構成を担当した作品である。作画は武富健治が手がけており、上下巻で完結する構成となっている。芸人の視点を持つ岩崎が関わることで、物語の中にある芸人のリアルな感情や空気感が、より立体的に描かれている。
物語は、売れない漫才師・徳永が、破天荒な先輩芸人・神谷と出会い、弟子入りを志願するところから始まる。二人の師弟関係を軸に、芸人としての生き方や葛藤、そして人間としての孤独や希望が描かれていく。構成では、原作の文学的な余韻を損なうことなく、漫画としてのテンポや視覚的な演出が丁寧に設計されている。
特に印象的なのは、漫才シーンの描写である。セリフの間や視線の動き、舞台上の空気感が細かく表現されており、読者はまるで客席からその場を見ているような感覚になる。芸人としての経験を持つ岩崎だからこそ、舞台の緊張感や芸人同士の微妙な距離感を的確に捉えることができている。
また、神谷という人物の破滅的な魅力と、徳永の常識的な視点との対比が、物語に深みを与えている。構成では、この二人の関係性が徐々に変化していく様子を、時間軸と心理描写を交錯させながら描いており、読者は自然と感情移入していく。終盤にかけての展開では、静かな諦めや切なさが漂い、読後に残る余韻が強く印象に残る。
漫画『火花』は、芸人という職業を通して人間の本質に迫る作品であり、構成と描写の両面で高い完成度を誇っている。原作を知らない読者でも、物語の世界に入り込みやすく、芸人という存在の奥深さを感じることができる作品となっている。
舞台脚本での構造と人物描写
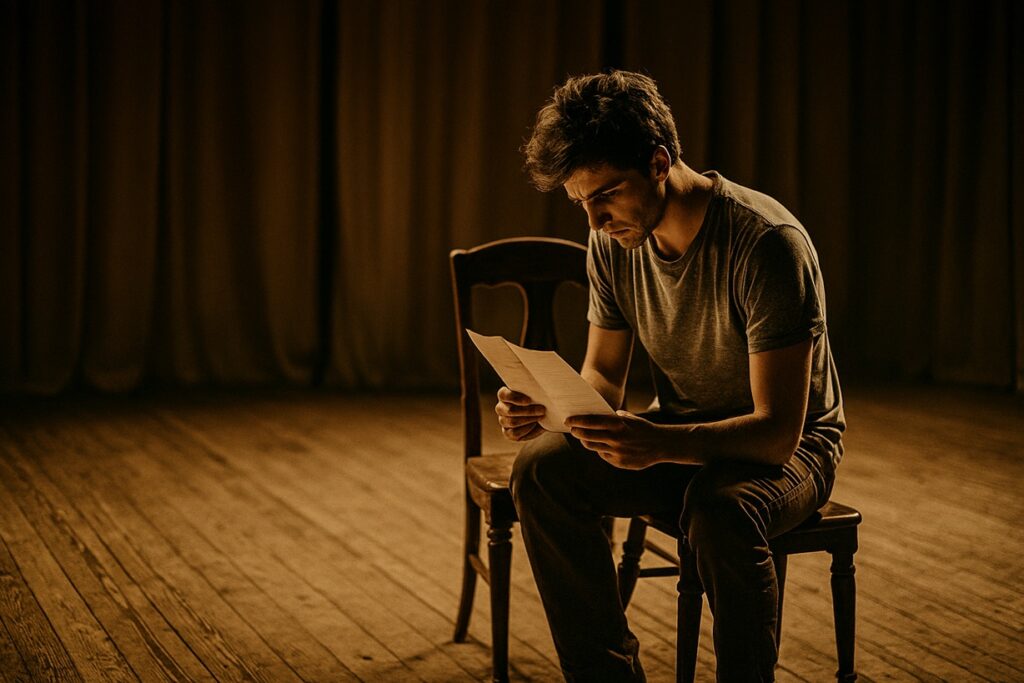
岩崎う大が手がける舞台脚本は、物語の構造と登場人物の心理描写に深く焦点を当てている。劇団かもめんたるの公演では、コメディを基調としながらも、登場人物の内面に迫る繊細な描写が随所に盛り込まれている。笑いの中にある切実さや、関係性の揺らぎを丁寧に描くことで、観客は物語に自然と引き込まれていく。
脚本の構造は、単純な起承転結にとどまらず、複数の視点や時間軸が交錯するような設計がなされている。登場人物の行動や言葉が、後の展開に伏線として作用する場面も多く、観客は物語の進行とともに人物の背景や感情を深く理解していく。こうした構成は、演劇ならではのライブ感と緊張感を高める要素となっている。
人物描写においては、表面的な性格だけでなく、過去の出来事や関係性の履歴が丁寧に織り込まれている。登場人物が抱える葛藤や迷いが、セリフや間の使い方によって浮かび上がり、観客の共感を誘う。特に、感情の爆発ではなく、静かな揺れを描く場面において、岩崎の演出は高い評価を得ている。
近年では、原作付きの舞台作品にも取り組んでおり、2024年には『甘美なる誘拐』の脚本・演出を担当している。複数の事件と人物が交錯するミステリー作品でありながら、登場人物の動機や感情の流れを重視した構成が特徴的である。物語の終盤に向けて、点と点が繋がっていく展開は、観客に強い印象を残す。
岩崎の舞台脚本は、笑いとドラマの境界を柔軟に行き来しながら、人間の複雑さを描き出す力を持っている。観客が登場人物に感情移入しやすい設計がなされているため、舞台作品としての完成度が高く、演劇ファンからも支持を集めている。
noteやYouTubeでの批評活動
岩崎う大は、noteやYouTubeを通じてお笑い賞レースのネタを理論的に分析する批評活動を展開している。芸人としての経験と脚本家としての構成力を活かし、ネタの構造や演出、キャラクターの設計などを多角的に掘り下げるスタイルが特徴である。
noteでは、M-1グランプリやR-1グランプリ、THE SECONDなどの大会に出場した芸人のネタを取り上げ、各組の構成や演技、テーマ性について詳細に分析している。単なる感想ではなく、どのような設計が観客に届きやすいか、どこに改善の余地があるかを明確に示す内容となっており、芸人志望者やお笑いファンから高い支持を得ている。
YouTubeでは「う大脳」というチャンネルを運営し、お笑いだけでなく映画や漫画、アニメなどのエンタメ作品を独自の視点で深掘りしている。特に「キングオブコント」終了後に行われるネタ批評は毎年注目を集めており、構成の妙や演技の精度、観客との距離感などを丁寧に解説している。視聴者は、ネタの裏側にある設計思想や演者の意図を知ることで、より深く作品を味わうことができる。
岩崎の批評は、芸人としての立場から発信されているため、実践的かつ具体的である。芸人を批評する芸人という立ち位置は稀有であり、表現者としての信頼感があるからこそ、批評が受け入れられている。また、批評の中には、若手芸人へのエールや可能性への言及も含まれており、育成的な側面も持っている。
このような活動を通じて、岩崎う大はお笑いの構造を言語化し、視聴者にとっての理解の手助けとなる存在となっている。批評という行為が、単なる評価ではなく、表現の奥行きを伝える手段として機能している点に、彼の表現者としての姿勢が表れている。
「キングオブう大」企画の意義

「キングオブう大」は、テレビ朝日系『しくじり先生』の特別企画として始まった若手芸人向けのネタ披露企画である。デビュー10年目以内の芸人を対象に、岩崎う大が審査員としてネタを見て、点数とともに詳細な批評を行うスタイルが特徴となっている。単なるコンテストではなく、育成と分析を兼ねた場として機能している。
この企画の最大の特徴は、岩崎がネタの構造や演技、テーマ性などを論理的に分析し、芸人に直接フィードバックを行う点にある。100点満点で採点されるが、点数以上に注目されるのがそのコメントの内容である。ネタのどこが機能していたか、どこに改善の余地があるかを具体的に指摘することで、芸人自身が自分の表現を見直すきっかけとなっている。
過去の出場者の中には、この企画を経て『キングオブコント』や『M-1グランプリ』などの賞レースで結果を残す芸人も多く、実力派芸人の登竜門としての役割を果たしている。視聴者にとっても、ネタの裏側にある設計や演者の意図を知ることで、笑いの奥行きを感じる機会となっている。
岩崎はこの企画を通じて、芸人としての経験と脚本家としての構成力を活かし、若手芸人の可能性を引き出すことに力を注いでいる。批評には厳しさもあるが、そこには作品への深い理解と敬意が込められており、芸人たちにとっては貴重な学びの場となっている。
「キングオブう大」は、単なるバラエティ企画ではなく、お笑いの未来を担う若手芸人にとっての成長の場であり、岩崎う大が芸人を批評する芸人として確立した立ち位置を象徴する企画である。
NHK朝ドラ「ばけばけ」
NHK連続テレビ小説「ばけばけ」は、2025年秋から放送されている作品で、怪談を愛し語り継いだ夫婦をモデルにした物語である。舞台は明治時代の島根・松江。外国人教師ヘブンと、没落士族の娘トキを中心に、さまざまな人々が交差する人間ドラマが描かれている。
岩崎う大はこの作品で、新聞記者・梶谷吾郎役として出演している。梶谷は、来日したヘブンに密着する自称・敏腕記者で、調子の良さと鋭い観察力を併せ持つ人物。小さな出来事も大きなニュースに仕立て上げる手腕を持ち、物語の中で時にトキの味方となり、また時には敵対するなど、複雑な立ち位置を担っている。
岩崎の演じる梶谷は、物語の進行において重要な役割を果たしており、登場するたびに場面に独特の緊張感とユーモアをもたらしている。出雲ことばを使ったセリフ回しや、記者としての立ち振る舞いには、岩崎ならではの演技の工夫が随所に見られる。視聴者からは、コミカルでありながらも芯のある人物像として印象に残るという声が多く寄せられている。
今回が岩崎にとって初の朝ドラ出演となり、本人も「人生頑張った甲斐があった」と語るほど、出演への喜びと意欲を見せている。撮影現場では、共演者との掛け合いを楽しみながら、役柄に深みを持たせる演技を追求している様子が伝えられている。
「ばけばけ」の中で梶谷吾郎というキャラクターは、物語の外側から内側へと入り込み、登場人物たちの感情や関係性を揺さぶる存在として描かれている。岩崎う大の演技は、その複雑な役柄を自然に体現し、ドラマ全体に豊かな彩りを加えている。
▶▶ 詳しくはこちらの記事もどうぞ
表現ジャンルを横断するスタンス

岩崎う大は、お笑い芸人としての活動を起点に、演劇、漫画、批評といった複数のジャンルを横断して表現を続けている。それぞれの分野で独自の視点を持ち、ジャンルの枠にとらわれない創作姿勢が際立っている。
お笑いでは、コンビ「かもめんたる」として2013年に『キングオブコント』で優勝。物語性のあるコントを得意とし、笑いの中に不穏さや哲学的な余韻を残す作風で注目を集めた。その構成力は、演劇や漫画にも通じるものがあり、ジャンルを超えて一貫した表現の軸となっている。
演劇では、2015年に「劇団かもめんたる」を旗揚げし、脚本・演出を担当。岸田國士戯曲賞の候補に2度選ばれるなど、演劇界でも高い評価を得ている。舞台作品では、登場人物の心理や関係性を丁寧に描きながら、物語の構造に緻密な設計を施している。笑いとドラマの境界を柔軟に行き来する演出は、観客の感情に深く訴えかける力を持っている。
漫画では、芥川賞作家・又吉直樹の『火花』の漫画化を構成担当として手がけたほか、自身のオリジナル作品も発表している。画力だけでなく、物語の展開や人物の描写においても、演劇的な感覚が活かされており、読者に強い印象を残す作品となっている。
批評活動では、noteやYouTubeを通じて賞レースのネタを分析し、芸人としての視点から構造や演技を言語化している。「キングオブう大」などの企画では、若手芸人のネタを理論的に評価し、育成的な役割も果たしている。芸人を批評する芸人という稀有な立ち位置を確立し、表現の裏側にある設計思想を伝える活動を続けている。
岩崎う大のスタンスは、ジャンルごとに異なる技法を使いながらも、根底にある「物語を描く力」によって統一されている。それぞれの分野で深く掘り下げた表現を行うことで、幅広い層の観客や読者に届く作品を生み出している。
岩崎う大の多面的な表現活動を通して見える輪郭
- 幼少期にオーストラリアで過ごした経験が創作の土台になっている
- 早稲田大学で演劇サークルに所属し表現力を磨いた
- 学生芸人グループWAGEで脚本を担当し葛藤を抱えた
- WAGE解散後にかもめんたるを結成し活動を再構築した
- 2013年にキングオブコントで優勝し注目を集めた
- 劇団かもめんたるでは脚本と演出を一手に担っている
- 岸田國士戯曲賞候補に2度選ばれ演劇界でも評価されている
- 漫画『火花』の構成を担当し文学作品を再構築した
- 自作漫画では人間の内面を描く作風が際立っている
- 若手芸人の育成企画「キングオブう大」で批評活動を展開している
- 賞レースの審査員としても理論的な視点で評価を行っている
- noteやYouTubeでお笑いの構造を言語化する活動を続けている
- NHK朝ドラ「ばけばけ」で新聞記者役として印象的な演技を見せた
- お笑い演劇漫画批評を横断するスタンスで表現を広げている
- 岩崎う大はジャンルを超えて物語を描く力を持っている
▶▶ こちらの記事もどうぞ
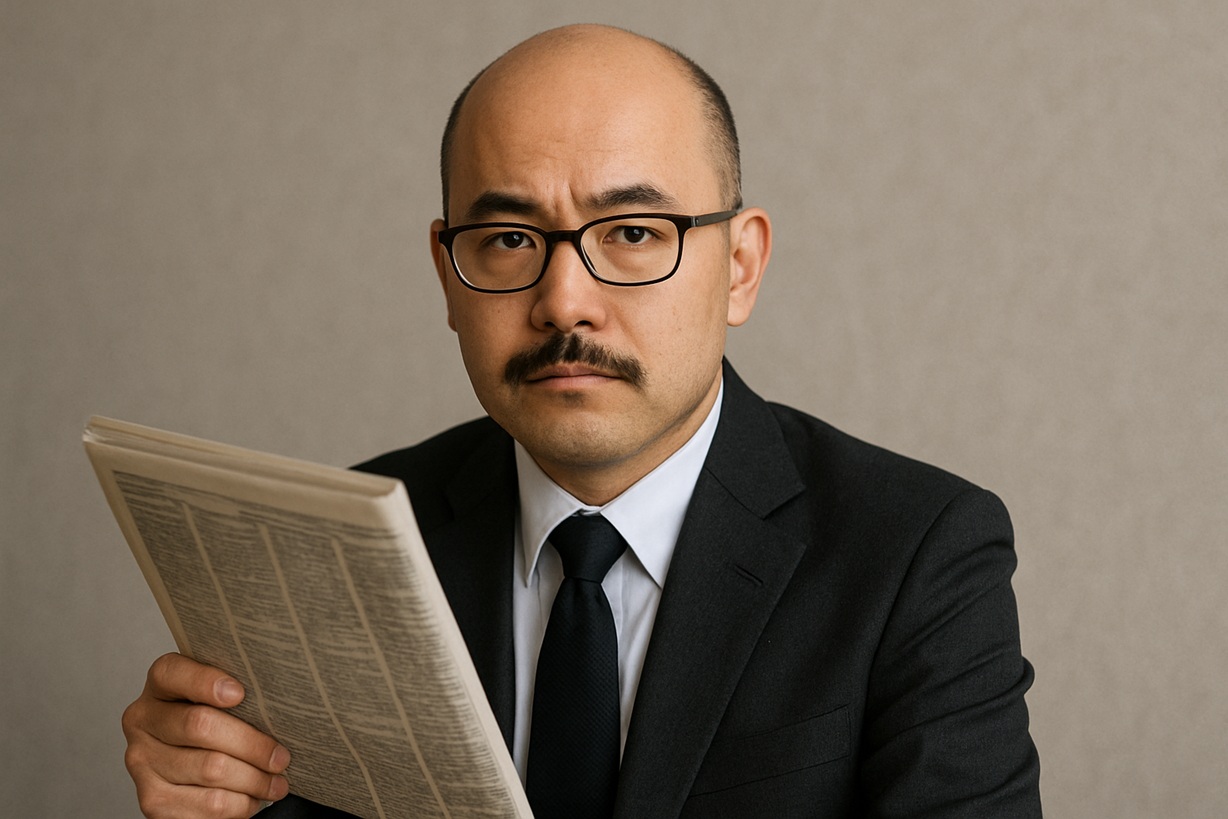





コメント