榛葉賀津也は、アメリカとイスラエルでの留学経験を通じて英語力を磨き、政治活動の中でその語学力を実践的に活かしてきました。
外務副大臣としての国際交渉や国際会議での発言、ミャンマー訪問時の対応、記者会見での英語補足など、通訳を介さずに直接対話する姿勢が信頼を集めています。語学力は単なるスキルではなく、政治的な説得力や国際的な発信力を支える基盤となっています。
その背景には、高校卒業後すぐに海外進学を選んだ強い意志と、異文化環境で培った柔軟な思考力があります。英語だけでなくヘブライ語も話せるトリリンガルとして、多言語対応力も注目されています。
SNSでも発音や表現力に対する肯定的な評価が多く、人物像の一部として語学力が認識されています。国際舞台で信頼を得る政治家の語学力とはどのようなものか、具体的な事例とともに紹介します。
【この記事のポイント】
- 榛葉賀津也が英語力を身につけた留学経験
- 外務副大臣としての英語による国際交渉の実例
- 英語力が記者会見や政党活動に活かされている背景
- SNSで語られる語学力への評価と信頼感
榛葉賀津也の英語力は留学経験が基盤
英語力の基礎となった高校卒業後の進路
榛葉賀津也は静岡県立掛川西高等学校を卒業後、アメリカ・オハイオ州にあるオタバイン大学へ進学しています。高校時代は野球部に所属し、三塁コーチとしてチームを支える立場にありました。補欠ながらも仲間との連携を重視し、裏方としての役割を果たす姿勢が印象的です。このような経験が、後の海外生活でも人との関係構築に活かされています。
高校卒業後すぐに海外の大学へ進むという選択は、当時としては珍しく、強い意志と準備が必要でした。オタバイン大学では政治学と国際問題研究を専攻し、現地の学生と同じ環境で学びながら、英語での授業や課題に取り組む日々を送っています。語学力だけでなく、異文化への理解や対応力も求められる環境で、実践的な英語力が自然と身についていきました。
大学生活の中で、英語を使って自分の考えを伝える機会が多くあり、語彙や表現力が磨かれていきます。また、イスラエルへの短期留学も経験しており、英語以外の言語にも触れることで、語学に対する柔軟性と応用力が育まれました。こうした積み重ねが、現在の英語力の土台となっています。
アメリカ・オタバイン大学での学び
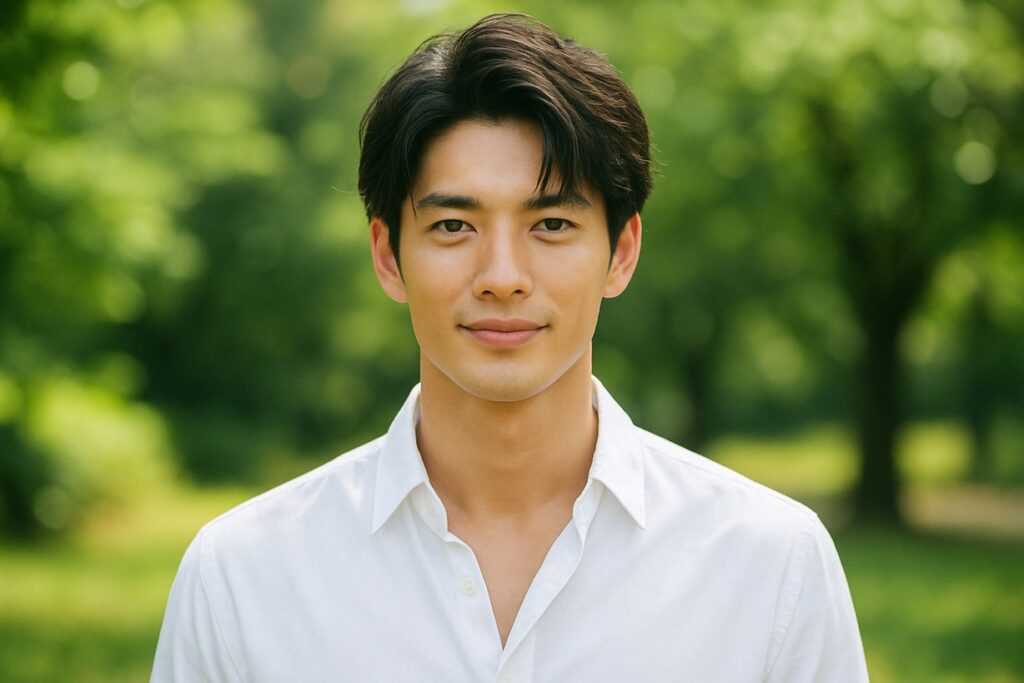
榛葉賀津也は高校卒業後、アメリカ・オハイオ州にあるオタバイン大学へ進学しています。この大学はリベラルアーツ教育を重視しており、少人数制の授業を通じて学生同士の対話や教員との距離の近さが特徴です。榛葉氏はここで政治学と国際問題研究を専攻し、現地の学生と同じカリキュラムで学びました。
授業はすべて英語で行われ、講義の理解だけでなく、レポートの執筆やプレゼンテーション、グループディスカッションなど、積極的に英語を使う場面が日常的にありました。こうした環境の中で、語学力は自然と鍛えられていきます。特に政治学という分野では、抽象的な概念や歴史的背景を英語で理解し、論理的に説明する力が求められます。
大学では、国際的な視点を持つ授業が多く、アメリカの政治制度だけでなく、世界各国の政治状況や外交政策についても学ぶ機会がありました。その中で、英語を通じて異なる価値観や文化に触れることができ、語学力とともに国際感覚も養われています。
また、オタバイン大学は留学生の受け入れにも積極的で、多様なバックグラウンドを持つ学生が集まる環境です。榛葉氏はその中で、日本人としての視点を持ちながら、他国の学生と意見を交わす経験を重ねてきました。こうした交流は、語学力だけでなく、対話力や柔軟な思考にもつながっています。
TOEFLスコアと入学時の英語力
榛葉賀津也は、アメリカのオタバイン大学に進学する際、TOEFLで530点を取得しています。このスコアは、当時の基準では中級レベルにあたり、英語での授業に対応できる力を示しています。大学の授業では、専門的な内容を理解するだけでなく、自らの考えを英語で表現する力が求められるため、入学時点で一定の語学力と論理的思考力を備えていたことがわかります。
TOEFLは、リーディング、リスニング、スピーキング、ライティングの4技能を測定する試験であり、単なる語彙力や文法力だけでなく、実際のコミュニケーション能力が問われます。榛葉氏がこの試験で合格水準を満たしていたことは、英語を使って学問を深める準備が整っていた証でもあります。
大学では政治学と国際問題研究を専攻しており、抽象的な概念や複雑な国際情勢について英語で議論する場面が多くあります。そのため、入学時の語学力は単なる基礎ではなく、思考を言語化する力としても重要な役割を果たしていました。こうした力は、後の政治活動や国際交渉の場面でも活かされています。
イスラエル留学で得た多言語環境

榛葉賀津也はアメリカの大学に在学中、イスラエルへの短期留学を経験しています。きっかけは、オタバイン大学の掲示板で見かけたテルアビブ大学の留学生募集案内でした。募集条件はアメリカ在住のユダヤ人向けでしたが、応募したところ特別枠として受け入れられ、イスラエルでの学びが実現しました。
テルアビブ大学では1年間を過ごし、その後オハイオへ戻って卒業しています。さらに、卒業後にはイスラエルのヘブライ大学大学院に進学し、国際政治学を2年間学んでいます。こうした経歴から、イスラエルでの滞在は短期にとどまらず、計3年間にわたる本格的な留学経験となっています。
イスラエルでは英語だけでなく、ヘブライ語にも触れる機会が多くありました。現地の生活や授業を通じて、日常会話レベルのヘブライ語を習得し、英語と日本語に加えて三言語を使い分ける力が身につきました。ヘブライ語は英語よりも発音や語順が日本語に近い部分もあり、榛葉氏にとっては親しみやすい言語だったようです。
異なる文化圏での生活は、語学力の応用力を高めるだけでなく、価値観や思考の幅を広げる経験にもなります。イスラエルという国の多様性や政治的背景に触れることで、国際問題への理解が深まり、語学力とともに政治家としての視野も広がっていきました。
英語での授業と議論の積み重ね
榛葉賀津也は、アメリカ・オタバイン大学で政治学と国際問題研究を専攻し、英語による授業を4年間受けています。授業では、講義を聞くだけでなく、課題の提出やプレゼンテーション、グループディスカッションなど、積極的に発言する機会が多くありました。こうした環境の中で、語彙力や表現力が自然と磨かれていきました。
政治学の授業では、国際情勢や外交政策など、抽象的かつ複雑なテーマを扱うことが多く、英語で論理的に意見を述べる力が求められます。榛葉氏は、現地の学生と対等に議論を交わしながら、自らの考えを英語で伝える力を身につけていきました。特に、国際問題に関する授業では、異なる視点を持つ学生との対話を通じて、柔軟な思考と説得力のある表現が養われています。
また、授業外でも英語を使う場面は多く、日常生活の中での会話や課外活動を通じて、実践的な語学力が定着していきました。英語を単なる学習対象としてではなく、思考や交流の手段として使い続けることで、語学力はより深く根付きます。
こうした経験は、後の政治活動においても活かされており、国際会議や外交の場面で英語を使って意見を述べる力の基盤となっています。
ヘブライ語も話せるトリリンガル

榛葉賀津也は、アメリカ留学中にイスラエルのテルアビブ大学へ特別枠で留学し、その後、ヘブライ大学大学院で国際政治学を学んでいます。イスラエルでの滞在は計3年間に及び、現地の生活や学びを通じて、ヘブライ語にも自然と親しむようになりました。
ヘブライ語は、英語よりも語順や発音が日本語に近い部分があり、榛葉氏にとっては馴染みやすい言語だったようです。現地では日常会話をこなすだけでなく、政治や国際問題に関する議論にも参加しており、実践的な語学力が身につきました。英語とヘブライ語を自在に使い分けることで、異なる文化圏の人々と直接対話できる力を得ています。
日本語、英語、ヘブライ語の三言語を扱えることは、国際的な場面での柔軟な対応力につながります。特に外交や国際会議の場では、通訳を介さずに意思を伝えることができるため、信頼性や説得力が高まります。語学力の幅広さは、政治活動においても重要な資産となっており、榛葉氏の国際的な発信力を支える要素のひとつです。
英語力を支える目的意識と実践
榛葉賀津也は、政治家として国際的な活動を視野に入れた学びを続けてきました。高校卒業後すぐにアメリカの大学へ進学し、政治学と国際問題研究を専攻したのも、将来的に外交や国際協力の分野で活躍することを見据えた選択です。語学力はそのための手段であり、目的意識を持って使い続けることで、実践的な力へと育っていきました。
大学では英語での授業を受けるだけでなく、現地の学生と議論を交わす機会も多くありました。さらに、イスラエルへの留学ではヘブライ語にも触れ、異なる言語環境での対応力を身につけています。こうした経験は、語学力を単なる知識ではなく、思考や対話の道具として使う力へと変えていきました。
政治家としての活動においても、英語力は重要な役割を果たしています。外務副大臣として国際会議に参加した際には、英語での意見交換や交渉に直接関わり、通訳を介さずに意思を伝える場面もありました。また、ミャンマー訪問時には現地の政党関係者と英語で会談を行い、国際的な課題に対する理解と対応力を示しています。
国民民主党の幹事長としても、海外との連携や国際的な発信が求められる場面が増えており、英語力は組織の信頼性を支える要素となっています。語学力を活かした実践の積み重ねが、榛葉氏の国際的な政治活動を支える基盤となっています。
榛葉賀津也の英語力が政治活動に活きる場面
外務副大臣時代の国際交渉経験

榛葉賀津也は、野田第3次改造内閣で外務副大臣を務めた際、国際会議や外交交渉の場に数多く立ち会っています。その中では、各国の外交官や政府関係者と直接英語で意見を交わす場面が多くありました。通訳を介さずに対話できることは、相手との距離を縮め、信頼関係を築くうえで大きな意味を持ちます。
国際交渉では、言葉のニュアンスや表現の選び方が交渉の結果に影響を与えることもあります。榛葉氏は、アメリカやイスラエルでの留学経験を通じて培った語学力を活かし、英語での議論や調整を円滑に進める力を発揮しています。特に、外交の現場では迅速な意思疎通が求められるため、英語で直接やり取りできることは、政策決定のスピードにもつながります。
また、ミャンマーの政党関係者との会談では、現地の状況や課題について英語で意見交換を行い、実務的な対応を進める場面もありました。こうした経験は、単なる語学力ではなく、国際的な視野と対応力を備えた政治家としての実績を示しています。
外務副大臣としての活動は、国際社会との関係構築において重要な役割を担っており、榛葉氏の英語力はその基盤として機能しています。語学力があることで、相手国の文化や価値観を理解しながら、より深い対話が可能となり、外交の質を高めることにもつながっています。
国際会議での英語による意見交換
榛葉賀津也は、外務副大臣としての任期中をはじめ、国際会議の場で英語によるスピーチや質疑応答を数多く経験しています。こうした場面では、政策や外交方針を明確に伝えるだけでなく、他国の代表と直接意見を交わす力が求められます。榛葉氏はその環境下で、英語を使って自らの考えを発信する力を発揮しています。
国際会議では、通訳を介さずに英語で発言することで、発言のニュアンスや意図がより正確に伝わります。榛葉氏は、アメリカとイスラエルでの留学経験を通じて培った語学力を活かし、外交の現場での発言においても、流暢な英語で対応しています。実際に、国際的な課題に関する議論では、英語での意見交換を通じて他国の代表と信頼関係を築いてきました。
また、英語による発信は、国際社会に対する日本の立場を明確に示す手段でもあります。榛葉氏は、国際会議での発言を通じて、日本の外交姿勢や政策提案を英語で伝えることで、国際的な理解と協力を促進する役割を果たしています。こうした活動は、語学力だけでなく、政治的な判断力と表現力が融合した成果といえます。
ミャンマー訪問時の英語活用事例

榛葉賀津也は外務副大臣としての任期中、ミャンマーを訪問し、現地の政党関係者や政府関係者との会談に臨んでいます。この訪問では、英語を用いて直接意見を伝える場面が多くありました。通訳を介さずに対話することで、相手の反応を即座に受け止め、柔軟に対応することが可能となります。
ミャンマーは多民族国家であり、政治的にも複雑な背景を持つ国です。現地の状況を理解するには、単なる情報収集だけでなく、現地の人々との対話を通じた感覚的な理解が重要です。榛葉氏は、英語を使って現地の課題や要望を直接聞き取り、それに対する政策的な提案を行うことで、実務的な対応力を示しています。
また、国際機関との連携においても、英語によるコミュニケーションは欠かせません。榛葉氏は、現地で活動する国際NGOや外交団との意見交換にも積極的に参加し、日本の立場や支援方針を明確に伝える役割を担っています。こうした活動は、語学力だけでなく、国際的な視野と政治的な判断力が融合した対応といえます。
ミャンマー訪問は、榛葉氏の語学力が実際の外交の現場でどのように活かされているかを示す具体的な事例のひとつです。英語を使って現地の人々と直接向き合う姿勢は、信頼の構築にもつながり、国際的な関係づくりにおいて重要な要素となっています。
記者会見での英語による補足説明
榛葉賀津也は、国民民主党の幹事長として定例記者会見に臨む際、日本語での発言に加えて英語での補足説明を行う場面があります。これは、国内向けの情報発信だけでなく、海外メディアや国際的な視聴者への配慮として行われており、発言の透明性と理解促進を目的とした対応です。
2025年4月の記者会見では、国際的な課題に関する発言の一部を英語で補足する姿が確認されています。このような対応は、英語を母語としない視聴者にとっても内容を把握しやすくする効果があり、政治家としての発信力を広げる手段となっています。特に、外交や安全保障に関するテーマでは、国際社会との連携を意識した発言が求められるため、英語による説明は重要な役割を果たします。
英語での補足説明は、単なる翻訳ではなく、文脈に応じた表現やニュアンスを含めた発言となっており、榛葉氏の語学力と政治的判断力が融合した対応といえます。こうした姿勢は、国際的な場面での信頼構築にもつながり、政治家としての発信力を高める要素となっています。
国民民主党幹部としての語学対応力

榛葉賀津也は、国民民主党の幹事長として、国内外の政治関係者との連携に関わる場面が多くあります。特に、海外の政党や外交関係者との交流では、英語による対応が求められることがあり、榛葉氏の語学力が組織の国際対応力を支える重要な要素となっています。
2025年以降、国民民主党は国際的な課題への関心を高めており、幹部としての榛葉氏は、英語を使って日本の立場や政策を説明する役割を担っています。記者会見では、国際的なテーマに関する発言の一部を英語で補足する場面も見られ、海外メディアへの配慮とともに、発信力の強化につながっています。
また、外交防衛委員会などの国会活動においても、海外の議員や関係機関との意見交換が行われることがあり、英語での対応力が求められます。榛葉氏は、アメリカとイスラエルでの留学経験を通じて培った語学力を活かし、通訳を介さずに直接対話することで、信頼関係の構築や迅速な意思疎通を実現しています。
こうした語学対応力は、政党としての国際的な信頼性にもつながっており、榛葉氏の存在が国民民主党の外交的な発信力を支える柱のひとつとなっています。語学力を活かした実践的な対応は、単なる言語能力を超えて、政治的な判断力と国際感覚を融合させた活動として評価されています。
SNSで語られる英語力への評価
榛葉賀津也の英語力は、SNS上でも注目されており、肯定的な評価が数多く見られます。特に、発音の自然さや表現の滑らかさに対して「通訳なしでも安心できる」「本物の国際派」といった印象を持つ声が寄せられています。実際に動画で英語を話す姿が公開されており、その流暢さが話題となっています。
英語での発言は、単に言葉を並べるだけでなく、論理的な構成力や説得力が伴っていることが評価されています。政治的なテーマに関する発言でも、英語での説明が明快であることから、国際的な場面での信頼感につながっていると受け止められています。
また、SNSでは「日本の政治家でここまで語学に堪能な人は珍しい」といったコメントも見られ、榛葉氏の語学力が人物像の一部として認識されています。英語だけでなくヘブライ語も話せることが知られており、多言語対応力が国際的な活動において強みとなっていることが伝わっています。
こうした評価は、留学経験や実務での語学活用が背景にあるからこそ生まれているものであり、語学力が単なるスキルではなく、政治家としての信頼性や発信力を支える要素として受け止められています。
通訳不要な場面での信頼感

榛葉賀津也は、英語を使って通訳を介さずに直接対話できる政治家として、国際的な場面で高い信頼を得ています。外交の現場では、言葉の選び方や表現のニュアンスが交渉の成否に影響を与えることがあり、通訳を通さずに自らの言葉で伝えることができる力は、相手国との距離を縮める重要な要素となります。
英語での直接対話は、発言の意図が正確に伝わるだけでなく、即座に反応できる柔軟性も生まれます。榛葉氏は、アメリカやイスラエルでの留学経験を通じて培った語学力を活かし、国際会議や外交交渉の場で、英語による発言を自ら行っています。こうした姿勢は、相手国の代表者からの信頼を得る要因となり、政治的な説得力にもつながっています。
また、通訳を介さないことで、発言のスピードやテンポが保たれ、議論の流れを途切れさせることなく進めることができます。これは、特に緊張感のある交渉や即時対応が求められる場面で効果を発揮します。榛葉氏の語学力は、こうした実務的な場面での対応力を支える基盤となっており、国際的な信頼構築においても大きな役割を果たしています。
榛葉賀津也の英語力が支える国際的な信頼と実践
- 高校卒業後すぐにアメリカの大学へ進学
- オタバイン大学で政治学と国際問題を専攻
- 英語での授業や議論を通じて語彙力を強化
- TOEFL530点で入学し基礎力を証明
- イスラエル留学でヘブライ語にも対応
- ヘブライ大学大学院で国際政治学を学習
- 英語とヘブライ語を使い分ける実践力
- 外務副大臣として英語で外交交渉を実施
- 国際会議で英語による意見交換を経験
- ミャンマー訪問時に英語で現地対応を実施
- 記者会見で英語による補足説明を実施
- 国民民主党幹部として英語で外交対応
- SNS上で発音や構成力への評価が多数
- 通訳不要な場面で信頼を得る語学力
- 英語力が政治活動の説得力を支える基盤
▶▶ よかったらこちらの記事もどうぞ





コメント