岩谷健司は、映画・ドラマ・舞台の垣根を越えて、静かな存在感と確かな演技力で物語の深度を支える俳優です。台詞の少ない場面でも視線や姿勢で人物の内面を描き出し、観る者の記憶に残る演技を重ねてきました。近年では『ロストケア』『スイート・マイホーム』など社会的テーマを扱う作品に出演し、映像の中で緊張感と余韻を生み出す役割を担っています。
また、山内ケンジとの長年にわたる舞台協働や、演劇ユニット「城山羊の会」「午後の男優室」での活動を通じて、台詞の間や沈黙を活かした独自の演技スタイルを確立。小劇場という空間で観客との距離感を意識した繊細な表現は、舞台俳優としての厚みを物語っています。
本記事では、岩谷健司の映像作品における役柄の幅、演出家との関係性、舞台での演技アプローチ、そして演出助手としての裏方経験までを丁寧に辿りながら、その演技力の本質に迫ります。コメディからシリアス、時代劇から現代劇まで自在に演じ分ける岩谷健司の魅力を、作品と演技の変化を通して紐解いていきます。
【この記事のポイント】
- 岩谷健司の映画・ドラマでの演技傾向
- 舞台での継続的な出演と演出家との関係
- コメディからシリアスまでの演技の幅
- 演出助手としての経験と舞台への理解
▶▶ 岩谷健司さんの作品をアマゾンプライムでチェックしてみる
岩谷健司の出演作品と映像での存在感
映画での印象的な役柄と演出家との関係
岩谷健司は、映画の中で物語の流れを支える役柄を数多く演じてきました。近年では『ロストケア』や『スイート・マイホーム』など、社会的なテーマや心理的な緊張感を含む作品に出演し、観客の記憶に残る演技を見せています。特定の演出家との継続的な協働も目立ち、山内ケンジ監督作品では、日常の中に潜む違和感や沈黙の力を活かした演技が印象的です。
台詞が少ない場面でも、視線の動きや身体の使い方で人物の内面を表現し、画面に深みを与えています。例えば、『新幹線大爆破』では緊迫した状況下での冷静な演技が物語の緊張感を支え、『世界は僕らに気づかない』では静かな役柄ながらも、感情の揺れを丁寧に描いています。
演出家との関係性においては、信頼を築きながら役作りに取り組む姿勢が見られます。山内ケンジ監督とは舞台でも長年にわたり協働しており、映画でもその関係性が演技に反映されています。演出の意図を汲み取りながら、作品の世界観に自然に溶け込む演技を重ねることで、観客に余韻を残す場面を生み出しています。
役柄の幅も広く、ヒューマンドラマからサスペンス、ホラーまでジャンルを問わず出演しており、それぞれの作品で異なる人物像を的確に演じ分けています。演出家との対話を重ねながら、役に必要な要素を丁寧に構築する姿勢が、安定した演技力につながっています。
連続ドラマでの脇役としての安定感

岩谷健司は、連続ドラマにおいて脇役として数多くの作品に出演してきました。刑事、上司、父親、社長、編集長など、物語の中で重要な立ち位置を担う役柄が多く、登場するだけで場面に緊張感や深みが加わる存在です。演技は常に抑制が効いており、過度な表現に頼ることなく、自然体で人物像を浮かび上がらせています。
たとえば『科捜研の女 season24』では、科学捜査の現場に関わる役として、冷静な表情と的確な台詞回しで物語のリアリティを支えています。『パンドラの果実』では捜査関係者として登場し、複雑な科学犯罪の背景に説得力を持たせる演技を見せています。『漂着者』では捜査一課長役として、物語の進行に欠かせない存在感を発揮しています。
また、『それってパクリじゃないですか?』や『僕の姉ちゃん』など、職場を舞台にしたドラマでは、部長や上司として登場し、主人公との関係性を通じて物語のテンポや空気感を調整する役割を担っています。台詞の少ない場面でも、視線や姿勢で人物の立場や感情を伝える演技が印象に残ります。
脇役としての出演が多い中でも、作品ごとに異なる人物像を的確に演じ分けており、視聴者にとっては「見たことがあるけれど、毎回違う顔を見せてくれる俳優」として認識されています。物語の主軸を支える役者として、安定感のある演技がドラマ全体の完成度を高めています。
NHK朝ドラ作品で見せた多面的な演技
岩谷健司はNHKのドラマやスペシャル番組において、時代劇から現代劇まで幅広い役柄を演じています。連続テレビ小説『なつぞら』では、アニメ制作会社の社員・島貫健太役として登場し、職場の空気を和らげる穏やかな人物像を表現しました。『ちむどんどん』では商社の社長役として、沖縄から上京した主人公たちとの関わりを通じて、社会的立場と人間味を併せ持つ演技を見せています。
スペシャルドラマ『みをつくし料理帖』では、江戸時代の料理屋の主人として登場し、時代背景に合わせた所作や語り口で、物語の世界観に深みを加えています。現代劇では『空白を満たしなさい』に出演し、再生と葛藤を描く物語の中で、静かな語りと抑えた表情で人物の内面を丁寧に表現しています。
また、2025年後期放送予定の連続テレビ小説『ばけばけ』では、借金取り・森山善太郎役として出演が予定されており、明治時代の島根を舞台にした物語の中で、時代性を反映した演技が期待されています。これまでの出演作でも、役柄に応じて話し方や立ち居振る舞いを細かく調整し、人物の背景や感情を自然に伝える演技が印象に残ります。
NHK作品では、物語のテーマや時代設定に合わせて演技の幅を広げながら、登場人物の内面に寄り添う表現を重ねています。視聴者にとっては、画面の中で静かに存在感を放つ俳優として、物語の深度を支える役割を果たしています。
▶▶ 詳しくはこちらの記事もどうぞ
コメディからシリアスまで幅広い演技領域

岩谷健司は、映像と舞台の両分野でジャンルを問わず演技の幅を広げてきました。コメディ作品では、Netflix配信の『罵倒村』に出演し、日常の延長線上にあるユーモアを自然に引き出す演技を見せています。表情の変化や台詞の間の取り方に工夫があり、笑いの中に人物の複雑な背景を感じさせる演技が印象的です。過剰な動きに頼らず、淡々とした会話の中に感情の揺れを織り込むスタイルが、作品の空気に深みを与えています。
シリアスな作品では、感情を抑えた演技で物語の緊張感を支えています。『ロストケア』では、介護と倫理をめぐる重いテーマの中で、静かな語り口と繊細な表情で人物の葛藤を描き出し、観客に深い余韻を残しました。『スイート・マイホーム』では、ホラー要素を含む物語の中で、言葉に頼らず恐怖や不安を伝える演技が際立っており、画面越しに緊張感が伝わってきます。
舞台でもジャンルの幅広さが際立っており、山内ケンジ演出の『勝手に唾ツバがでる甘さ』では、日常の違和感を笑いに変える演技を披露しています。淡々とした会話の中に生々しい感情が見え隠れする構成の中で、岩谷健司は観客の笑いと共感を引き出す役割を担っています。一方、『夜明けの夫婦』では、夫婦の再生を描く静かな物語に寄り添い、抑制された演技で人物の内面を丁寧に表現しています。
演出家との継続的な協働の中で、作品ごとに異なる演技アプローチを柔軟に取り入れている点も特徴です。映像でも舞台でも、作品の空気に合わせて演技を変化させることで、人物の内面に寄り添いながら物語の奥行きを支えています。ジャンルに縛られず、作品の本質に向き合う姿勢が、岩谷健司の演技に一貫して見られます。
近年の出演作とその傾向
岩谷健司は近年、社会的なテーマを扱うドラマや映画への出演が目立っています。家庭、職場、地域社会など、身近な問題を描く作品の中で、登場時間が短くても印象に残る演技を見せることで、物語全体の厚みを支えています。
2023年以降の出演作には、『ロストケア』『スイート・マイホーム』『世界は僕らに気づかない』など、倫理や家族、社会のひずみを描く作品が並びます。『ロストケア』では介護をめぐる葛藤を描いた物語の中で、静かな語りと抑制された表情で人物の内面を表現し、観客に深い余韻を残しました。『スイート・マイホーム』では、ホラー要素を含む家庭の物語に登場し、恐怖と不安を言葉に頼らず伝える演技が印象的です。
テレビドラマでは、『それってパクリじゃないですか?』『僕の姉ちゃん』『パンドラの果実』『闇バイト家族』などに出演し、職場や社会の中で起こる問題に関わる役柄を演じています。たとえば『それってパクリじゃないですか?』では、知的財産をめぐる企業内の葛藤を描く物語の中で、上司として登場し、物語の緊張感を支える役割を果たしています。『闇バイト家族』では、社会の底辺に生きる人々の再生を描く中で、複雑な人間関係に関わる人物として登場しています。
また、『9ボーダー』では、人生の節目を迎える女性たちの物語に登場し、世代を超えた関係性の中で、人物の背景を感じさせる演技を見せています。『科捜研の女 season24』では、科学捜査の現場に関わる役として、冷静な立ち居振る舞いで物語のリアリティを支えています。
これらの作品に共通するのは、現代社会の中で誰もが直面しうる問題を描いている点です。岩谷健司は、そうした物語の中で、過剰にならず自然な演技を貫くことで、視聴者の共感を呼び、作品の完成度を高めています。
NetflixやWOWOWなど配信作品への参加

岩谷健司は、NetflixやWOWOWをはじめとする配信プラットフォームの作品にも積極的に出演しています。映画館や地上波テレビとは異なる視聴環境に合わせて、演技の細部に工夫を凝らし、画面越しでも伝わる繊細な表現を重ねています。
Netflixでは、2025年配信のコメディ作品『罵倒村』に出演しており、日常の中に潜む違和感や笑いを自然な演技で引き出しています。台詞の間や表情の変化を活かした演技は、スマートフォンやタブレットなど小さな画面でも人物の感情が伝わるように設計されており、視聴者の集中を途切れさせない工夫が見られます。
WOWOWでは、連続ドラマ『東野圭吾「さまよう刃」』や『有村架純の撮休』などに出演し、物語の中で静かな存在感を放っています。特に『さまよう刃』では、重厚なテーマに対して抑制された演技で物語の緊張感を支え、画面に深みを与えています。『有村架純の撮休』では、俳優の日常を描く中で、自然体の演技が作品のリアリティを高めています。
配信作品では、視聴者が一人で静かに鑑賞するケースが多いため、演技のトーンやテンポにも配慮が必要です。岩谷健司は、そうした環境に合わせて、過剰にならない演技を心がけながら、人物の内面を丁寧に描いています。映像の質感や編集のテンポに合わせて演技を調整することで、作品の完成度を高めています。
今後も配信作品への出演が続く中で、岩谷健司の演技はさらに多様な視聴スタイルに対応していくと考えられます。映像表現の幅を広げながら、観る人の心に静かに届く演技を重ねていく姿勢が、配信時代の俳優としての存在感を支えています。
役柄に応じた演技の変化と工夫
岩谷健司は、登場する役柄に応じて話し方や姿勢、視線の使い方を細かく調整しながら演技を組み立てています。刑事や編集長、社長など、同じ職業でも作品ごとに異なる人物像を演じ分けることで、画面にリアリティをもたらしています。
たとえば『科捜研の女』では、捜査関係者として冷静で理知的な態度を保ちつつ、緊迫した場面では視線の動きや口調に緩急をつけることで、状況の深刻さを伝えています。一方、『インビジブル』では編集長役として登場し、言葉の選び方や姿勢に柔らかさを加えることで、職場内の人間関係に配慮する人物像を描いています。
また、『それってパクリじゃないですか?』では企業の上司として、部下との距離感を意識した演技が見られます。言葉の抑揚や間の取り方に工夫があり、厳しさの中にも理解を示す人物像が浮かび上がります。『僕の姉ちゃん』では、同じく上司役ながらも、日常的な会話の中にユーモアを織り交ぜる演技で、職場の空気を和らげる存在として描かれています。
舞台作品でも、演出家との対話を通じて役柄の解釈を深め、人物の背景に合わせた演技を展開しています。山内ケンジ演出の舞台では、台詞の間や沈黙を活かした演技が特徴で、観客に人物の内面を想像させる余白を残しています。細部へのこだわりが、舞台と映像の両方で説得力のある人物像を生み出しています。
岩谷健司の演技は、表面的な動きにとどまらず、人物の立場や感情に寄り添った表現を重ねることで、作品の世界観に深く溶け込んでいます。役柄に応じた変化と工夫が、観る人の記憶に残る演技につながっています。
▶▶ 岩谷健司さんの作品をアマゾンプライムでチェックしてみる
岩谷健司の舞台活動と演劇ユニットでの歩み
「城山羊の会」での継続的な出演

岩谷健司は、演出家・山内ケンジが主宰する演劇ユニット「城山羊の会」において、2000年代から現在に至るまで継続的に出演を重ねています。『葡萄と密会』『効率の優先』『自己紹介読本』『温暖化の秋』『萎れた花の弁明』『勝手に唾がでる甘さ』など、毎年のように新作に参加しており、ユニットの中心的な俳優として位置づけられています。
このユニットの作品は、日常の会話をベースにしながらも、どこか不穏で奇妙な空気を漂わせる独特の作風が特徴です。台詞のテンポや沈黙の使い方、人物同士の距離感など、細部にわたる演出が求められる中で、岩谷健司はその空気を的確に捉え、観客に違和感と共感を同時に届ける演技を見せています。
たとえば『温暖化の秋』では、社会問題を背景にした会話劇の中で、淡々とした語り口の中に人物の不安や苛立ちを滲ませる演技が印象に残ります。『萎れた花の弁明』では、登場人物の言動に潜む矛盾や葛藤を、表情や間の取り方で丁寧に描き出しています。最新作『勝手に唾がでる甘さ』でも、日常の中に潜む不条理を自然な演技で浮かび上がらせています。
長年にわたる出演を通じて、岩谷健司は「城山羊の会」の世界観を深く理解し、演出家との信頼関係の中で演技を磨いてきました。観客との距離を意識した演技は、小劇場という空間において特に効果的で、舞台上の空気を繊細に変化させる力を持っています。継続的な参加によって、作品ごとのテーマや構造に対する洞察が深まり、演技の厚みにつながっています。
演劇ユニット「午後の男優室」の結成背景
「午後の男優室」は、岩谷健司が1999年に劇団「ワハハ本舗」を退団した後、自ら立ち上げた演劇ユニットです。俳優・村松利史、岡部たかしとともに結成され、演出家を招かずに俳優自身が創作の中心となるスタイルを特徴としています。舞台上での関係性や対話の密度を重視し、俳優同士の呼吸や間合いを軸にした作品づくりを目指して活動を続けています。
このユニットの発表作品には、『午後の男優室発表会』『もずく酢』『登戸』『零点大将』などがあり、いずれも日常の中に潜む違和感や人間関係の微細な揺れを描く内容が中心です。演出は村松利史が担当することが多く、俳優の視点から構成された舞台は、観客との距離が近い小劇場での上演に適した空気感を持っています。
結成の背景には、岩谷健司自身の演技に対する探究心が強く反映されています。既存の演出スタイルにとらわれず、俳優が主体となって作品を生み出すことで、演技の可能性を広げたいという意志が感じられます。舞台上での関係性を丁寧に構築することで、台詞や動きの一つひとつに説得力が生まれ、観客に深い印象を残す演劇空間が生まれています。
「午後の男優室」は、岩谷健司の俳優としての原点とも言える場であり、以降の舞台活動や演出家との協働にもつながる重要な足がかりとなっています。演技を通じて人間の複雑さを描き出す姿勢は、現在の映像作品や他の演劇ユニットでの活動にも通底しています。
山内ケンジ作品での演技スタイル
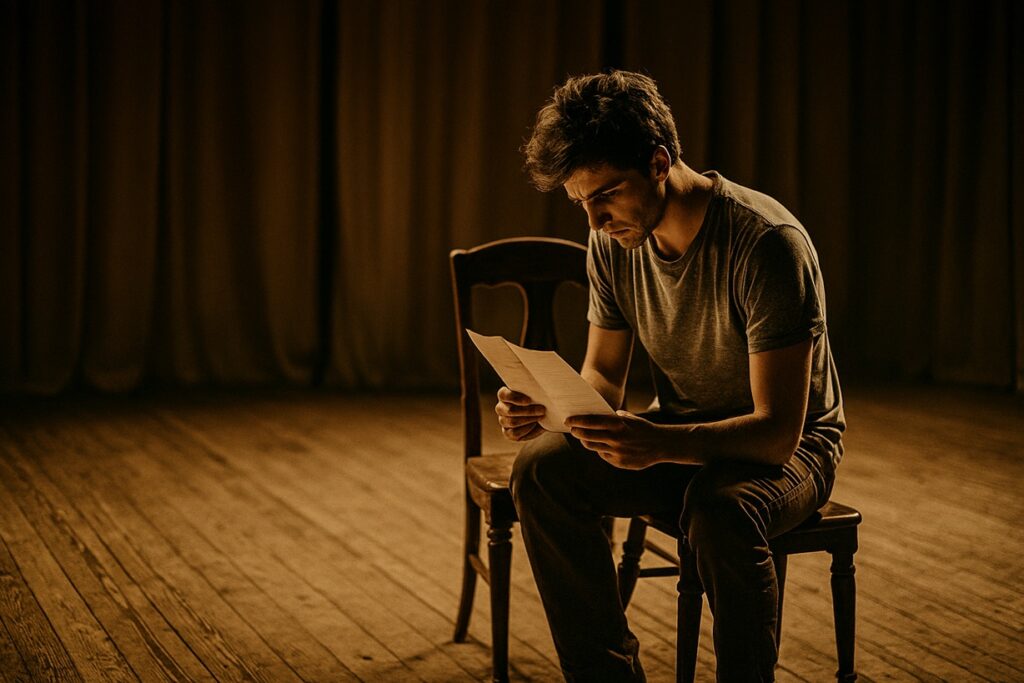
岩谷健司は、山内ケンジが作・演出を手がける舞台作品において、独特な演技スタイルを確立しています。山内作品は、日常の会話をベースにしながらも、どこか不穏で奇妙な空気を漂わせる構成が特徴で、台詞の間や沈黙が物語の緊張感を生み出す重要な要素となっています。岩谷健司はその空気を的確に捉え、観客に余韻を残す場面を多く生み出しています。
たとえば『温暖化の秋』では、淡々とした会話の中に生々しい感情が見え隠れする演技が印象的で、人物の不安や苛立ちを台詞の抑揚や間の取り方で丁寧に表現しています。『萎れた花の弁明』では、登場人物の言動に潜む矛盾や葛藤を、静かな語り口と視線の動きで浮かび上がらせています。最新作『勝手に唾が出てくる甘さ』でも、日常の中に潜む違和感を自然な演技で描き出し、観客に思わず笑いと戸惑いを同時に感じさせる場面を作り出しています。
山内ケンジの演出は、俳優との呼吸を重視し、台詞のテンポや沈黙の使い方に細かな指示が加えられることが多くあります。岩谷健司はその演出意図を的確に汲み取り、舞台上での動きや表情に反映させることで、作品の世界観を体現しています。演技の抑制と緊張感のバランスを保ちながら、観客に人物の内面を想像させる余白を残す演技は、山内作品において欠かせない存在となっています。
また、山内作品は欧米の演劇や映画に影響を受けた構造を持ちつつも、日本語による会話劇として独自の世界観を築いています。その中で岩谷健司は、言葉の意味だけでなく、言葉の裏にある感情や関係性を演技に落とし込むことで、観客との距離を縮めています。演出との信頼関係の中で生まれる演技は、作品の完成度を高める重要な要素となっています。
小劇場での活動と観客との距離感
岩谷健司は、小劇場という限られた空間の中で、観客との距離感を意識した演技を長年にわたって積み重ねています。舞台と客席の物理的な近さは、俳優の表情や動きの細部まで観客に届くため、演技の精度が求められる環境です。その中で岩谷健司は、過剰な動きに頼ることなく、自然な所作と繊細な感情表現で物語に引き込む力を発揮しています。
「城山羊の会」や「午後の男優室」などのユニットでの活動では、日常会話をベースにした作品が多く、観客が登場人物の一挙手一投足に集中する構造が特徴です。岩谷健司は、台詞の間や沈黙を活かしながら、人物の内面を静かに浮かび上がらせる演技を重ねています。視線の動きや呼吸の変化といった微細な表現が、観客の感情に直接働きかける場面を生み出しています。
たとえば『萎れた花の弁明』では、登場人物の葛藤や不安を、言葉に頼らず身体の緊張や姿勢の変化で伝える演技が印象に残ります。『勝手に唾が出てくる甘さ』では、日常の中に潜む違和感を、淡々とした語り口の中に織り込むことで、観客に思わず笑いと戸惑いを同時に感じさせる空気を作り出しています。
小劇場では、観客の反応が舞台上に直接届くため、演技のテンポや感情の流れをその場で調整する柔軟さも求められます。岩谷健司は、舞台上の空気を繊細に読み取りながら、演出家との呼吸を合わせて演技を構築しています。空間の特性を活かした演技は、観客との距離を縮め、物語への没入感を高める要素となっています。
こうした積み重ねにより、岩谷健司は小劇場という場において、観客の記憶に残る演技を継続的に生み出しています。舞台と客席の境界を越えて、人物の感情が届く瞬間を作り出す力が、俳優としての評価につながっています。
演出助手としての裏方経験

岩谷健司は俳優としての活動に加えて、演出助手として舞台制作の裏側にも深く関わってきました。2000年代以降、吹越満が主宰する「フキコシ・ソロ・アクトライブ」では、演出補助や創作ブレインとして複数の作品に参加しています。『mr.モーションピクチャー』『XVIII』『タイトル未定』『スペシャル』『ポリグラフ 嘘発見器』などの舞台で、演出の意図を共有しながら、構成や演技の調整に携わっています。
演出助手としての経験は、舞台の構造や演出家の視点を理解する機会となり、俳優としての演技にも大きな影響を与えています。舞台上での動きや台詞のテンポだけでなく、照明や音響、舞台美術との連携を意識した演技が可能となり、作品全体の完成度を高める役割を果たしています。
また、演出助手としての立場から俳優陣とのコミュニケーションを重ねることで、舞台上での関係性の構築にも貢献しています。演出家と俳優の間に立ち、演技の方向性を調整する役割を担うことで、舞台全体のバランスを整える視点が養われています。
このような裏方経験は、岩谷健司が演技に対して多角的な視点を持つ理由のひとつです。俳優として舞台に立つ際にも、演出の意図を踏まえた演技が自然にできるようになり、観客にとっても作品の世界観がより明確に伝わる演技につながっています。
ふじきみつ彦作品との関わり
岩谷健司は、劇作家・ふじきみつ彦が脚本を手がける舞台作品において、独特な台詞回しや人物設定に的確に対応する演技を重ねています。ふじき作品は、日常の中に潜む違和感や滑稽さを描きながら、登場人物の切実な感情を浮かび上がらせる構成が特徴です。岩谷健司はその世界観に寄り添い、笑いの中にある哀しみや緊張感を丁寧に表現しています。
演劇ユニット「切実」での活動は、ふじき作品との関係を象徴する場となっています。『朝の人』では、佐渡島のバス停で偶然出会った人物同士の奇妙な交流を描く中で、岩谷健司は観光客・早川役を演じ、静かな語り口と繊細な表情で物語の空気を支えました。登場しただけで笑いが起こるような存在感を持ちながらも、物語の終盤では孤独や切なさをにじませる演技で観客の感情を揺さぶっています。
また、『つばめ』『朝の人』『婚約者』など、ふじきみつ彦が脚本を担当した短編作品群でも、岩谷健司は台詞の間や沈黙を活かした演技で、人物の内面を浮かび上がらせています。ふじき作品では、台詞のテンポや言葉の選び方が独特であるため、俳優には高い柔軟性と感覚が求められます。岩谷健司は、言葉の裏にある感情や関係性を読み取り、舞台上で自然に体現することで、脚本の意図を的確に伝えています。
ふじきみつ彦との協働は、岩谷健司にとって演技の幅を広げる貴重な機会となっており、コントと演劇の境界を越えた表現に挑戦する場でもあります。笑わせようとするのではなく、人物の切実さを描くことで生まれる笑いを大切にする姿勢が、ふじき作品における岩谷健司の演技の核となっています。
近年の舞台出演と演出家との関係性

岩谷健司は近年、複数の演出家と継続的に協働しながら、舞台作品に出演を重ねています。演出家ごとの作風に合わせて演技スタイルを柔軟に調整し、作品の完成度を高める役割を担っています。演出意図を的確に汲み取りながら、俳優としての個性を抑えすぎずに活かすことで、舞台の質を支える存在となっています。
代表的な協働関係としては、山内ケンジとの長年にわたる取り組みが挙げられます。演劇ユニット「城山羊の会」では、『温暖化の秋』『萎れた花の弁明』『勝手に唾がでる甘さ』など、毎年のように新作に出演しており、台詞の間や沈黙を活かした演技で作品の空気を支えています。山内作品では、日常の中に潜む違和感や緊張感を表現する演技が求められ、岩谷健司はその世界観に自然に溶け込む演技を重ねています。
また、岡部たかしとの協働も継続的に行われており、演劇ユニット「切実」では『朝の人』『遊歩道』『川端』などに出演しています。ふじきみつ彦の脚本を岡部が演出する構成の中で、岩谷健司は人物の切実さや滑稽さを繊細に表現し、観客に深い印象を残しています。演出家との信頼関係の中で、台詞のテンポや感情の流れを調整する柔軟さが際立っています。
さらに、ケラリーノ・サンドロヴィッチ演出による『Don’t freak out』(ナイロン100℃)や、岩崎う大演出の『君しか見えないよ』など、異なる演出家の作品にも参加し、それぞれの舞台で異なる演技アプローチを見せています。ジャンルや演出スタイルに応じて、演技のトーンや身体の使い方を調整することで、作品の世界観に寄り添う演技を実現しています。
こうした継続的な協働は、演出家との信頼関係に支えられており、岩谷健司の演技に深みと安定感をもたらしています。舞台上での関係性や空気を丁寧に構築する姿勢が、観客にとっても物語への没入感を高める要素となっています。
岩谷健司の演技と活動を通して見える舞台力
- 映画では台詞の少ない場面でも印象を残す
- 連続ドラマで安定感のある脇役を多数演じている
- NHK作品では時代劇と現代劇の両方に対応している
- コメディとシリアスを自在に演じ分けている
- 社会的テーマを扱う作品への出演が増加している
- 配信作品では視聴環境に合わせた演技を工夫している
- 同じ職業でも人物像を演じ分ける技術がある
- 「城山羊の会」で長年にわたり主要な役を務めている
- 「午後の男優室」では俳優主導の創作に取り組んでいる
- 山内ケンジ作品では沈黙と間を活かした演技が光る
- 小劇場では観客との距離感を意識した演技を重ねている
- 演出助手として舞台構造への理解を深めている
- ふじきみつ彦作品では台詞のテンポに柔軟に対応している
- 複数の演出家と継続的に協働し演技を調整している
- 舞台と映像の両方で作品の世界観に寄り添っている





コメント